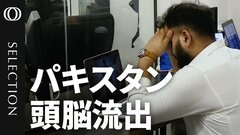(ブルームバーグ):日本銀行が9月に開いた金融政策決定会合では、利上げに向けた議論に広がりが見られる一方で、データを見極めるべきだといった慎重な意見も政策委員から示された。「主な意見」を30日に公表した。
ある委員は経済・物価が日銀見通しに沿っているとし、「大きく軌道を外れなければ、ある程度定期的な間隔で政策金利の水準を調整していくべきだ」と主張。米関税への不安が後退し、海外要因の制約が解消に向かう中、「再び利上げスタンスに回帰し、海外対比で低水準の実質金利の調整を行い得る状況」との意見も出た。

別の委員は、前回の利上げから半年以上が経過していることもあり、「そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない」と語った。ただ、この委員は米国経済の落ち込みの程度のめどがついていないとし、「当面の金融政策運営は現状維持が適当」とした。
9月会合では0.5%の政策金利の維持を決めたが、高田創、田村直樹の審議委員2人が利上げを主張して反対。最も利上げに慎重とみられていた野口旭審議委員も29日の講演で、政策調整の必要性に言及した。9月会合での議論は早期利上げを意識させる内容だったものの、市場で観測が高まっている10月利上げの決め手とはならなかった。
野村証券の岩下真理エグゼクティブ金利ストラテジストは電話取材で、9月会合の主な意見は「利上げに対して両論併記で、10月か12月か決め打ちできない」と指摘。その上で、植田和男総裁が3日の講演で利上げに前向きな姿勢を示せば、現在7割近い「10月利上げ織り込みを一段と引き上げる」との見方を示した。
ある委員は「市場にサプライズとなる現時点での利上げは避けるべきだ」と主張。日本経済の特徴として、内需が外的な負のショックに対しぜい弱な傾向があるとし、「金利の正常化を進める上では、ハードデータをもう少し確認してから判断しても遅くない」との意見もあった。
もっとも、物価に関する見解は上振れリスクへの警戒感がにじむ内容になっている。植田総裁は同会合後の記者会見で、政策判断で重視する基調的な物価上昇率について、2%を少し下回っているが、「2%に向けて近づきつつある」との見解を示した。
ある委員は、物価の基調は2%定着へ着実に歩みを続けるとし、「今後の財政政策の影響を含め、上振れリスクも大きい」と指摘。輸入物価が落ち着く中でも一部の企業は値上げに積極的であり、「消費者の購買状況次第では、値上げの流れに変化が生じることもあり得る」との声も出た。
他の「主な意見」
- 経済・物価見通し実現していけば、引き続き利上げ
- 物価との関係、待つことのコストも大きくなっていく
- 急激な利上げショック回避へ中立金利に近づけておくべきだ
- 0.5%までの利上げの経済全体への影響は極めて限定的
- 物価安定目標はおおむね実現、すでに物価上がらないノルムが転換
ETF売却
同会合では上場投資信託(ETF)の処分も決め、バランスシートの正常化を一段と進める。市場への影響に配慮し、簿価で年間3300億円程度のペースで売却する。植田総裁は会見で、「100年後にわれわれはいないが、100年以上かけて売っていくつもりだ」と語った。
政策委員からは、マイナス金利政策の終了や国債買い入れの減額から時間がたち、「ETFなどの処分にも踏み出すタイミングが来ている」との見解が示された。市場に影響を与えないように処分するためには、「完了まで長期間かかるのはやむを得ない」との意見も出た。
(詳細や市場関係者のコメントを追加して更新しました)
--取材協力:日高正裕.
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.