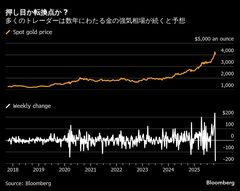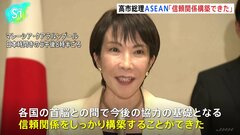本年6月に公表された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2025」では、財政健全化目標(フロー)に関して、「2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたPB黒字化を目指す」とされ、従来「2025年度」としていた目標年度を後退させた。
「プライマリー・バランス(PB)」は「基礎的財政収支」とも言われ、社会保障や公共事業などの政策的経費を、借金によらず税収等で賄えているかどうかを示す指標だ。
PBが赤字(マイナス)ということは、政策的経費を税収等で賄えず、国債等の借金にも頼っている状況を示す。
国と地方を合わせた我が国のPBは、バブル崩壊後の1992年から30年以上一貫して赤字が続いており、この間の日本の総債務は1000兆円以上増加している。
政府の財政健全化目標にPB黒字化が据えられるようになったのは、21世紀初頭、当時の小泉内閣で初めて取り纏められた「骨太の方針2001」であった。
また翌年の「骨太の方針2002」では、具体的に「2010年代初頭」での黒字化を目指すとされた。さらに「骨太の方針2006」では、「2011年度」に「確実に黒字化」するとした。
その後、リーマンショック(2008年)や東日本大震災(2011)による大型の財政出動もあり、第二次安倍政権最初となる「骨太の方針2013」では、「2020年度」までの黒字化とされた。
経済成長を重視した同政権は当初2015年に予定されていた消費税率10%への引き上げを2度延期(2019年10月実施)したなか、目標年度が近づいてきた「骨太の方針2018」において、黒字化の目標を「2025年度」に先延ばしし、冒頭の「骨太の方針2025」に至っている。
21世紀のスタートとともに、財政健全化目標としてPBの黒字化が据えられてちょうど四半世紀経つが、その経緯は逃げ水のようであった。
もちろん前述のように、経済危機や震災、コロナといった特殊要因があったのは事実であるが、例えば国の足元の歳出規模は、コロナ前を依然2割以上上回っている。緊急対策として計上したはずの予算が一部既得権益化し、なかなか元に戻せない様を示す一例であろう。
既得権といえば、毎年秋から冬にかけて編成される補正予算自体がそうなっていると言える。
そもそも補正予算は「特に緊要となった経費の支出」(財政法29条)に限ると規定されているものの、1947年の同法施行以降、補正予算が組まれなかった年はない。
ただ25年度のPB黒字化に関しては、昨年夏の時点では射程に入っていた。
内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」(2024年7月)によると、25年度のPBは+0.1%(対GDP比、以下同じ)と実に33年ぶりに黒字化を成し遂げる見通しになっていた。
しかし、13兆円を超える24年度補正予算等を反映した、今年1月の同試算では25年度のPBは▲0.7%と一転して赤字見通しとなった。
折しも先の参議院選では、何らかの消費税減税を掲げる野党が昨年の衆議院選に続いて過半数を獲得し、自公政権は衆参ともに少数与党となった。
与党も現金給付を公約に掲げており、今秋も「恒例」となった補正予算が編成される可能性が高いだろう。
さらに、2026年度予算の概算要求基準においては、重要政策への予算増額にあたって条件としてきた既存経費の削減を不要とした。
残念ながら、先の選挙戦では減税の財源や増大する社会保障費等に関する議論は十分とは言えなかった。
PB黒字化目標は、次の四半世紀も逃げ水のように漂流してしまうのだろうか。
目下の日本にそうした余裕はなく、この節目に一度目標と工程について“与野党”で棚卸と認識の共有を図ることは重要と考える。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 常務取締役経済調査部長 松村 圭一)