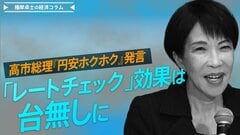今後の課題
中国における直近の育児手当や子育て支援関連の動きを振り返ると、2024年7月に開催された第20期3中全会で、出産・育児支援制度の確立が人口対策の重要施策として位置づけられている。
更に、2024年10月には「出産・育児支援政策システムの整備を加速し、出産・育児にやさしい社会づくりを推進するための諸施策」が発表され、3歳未満の乳幼児の保育費用について個人所得税免除を1人あたり月額2,000元に引き上げる策や、産休・育休の延長(合計158日)、男性が取得できる「配偶者出産休暇」(15日ほど)、3歳以下の子どもの看護休暇(5~20日)の新設や普及についても言及している。
2025年3月の全国人民代表大会後の政府活動報告でも、育児手当制度の創設と手当支給への言及があり、7月初旬には制度の近日中の正式発表が報道されていた。
子育て支援や育児手当に関する政府の政策的な機運は高まっている。
今回の全国統一の育児手当制度の導入は、国の出産・子育て支援策として大きな一歩と言える。しかし、今後に向けていくつかの課題も指摘されている。
まず、支給額は養育を賄うには不足しており、支給期間も短い点である。平均養育費をみると、4歳から高校を卒業する18歳までは439,698元(約900万円)、大学進学となると更に平均142,000元(約290万円)が必要となる。
まさに子どもの養育費がピークとなる時期についてはサポートがない状況にある。
また、現金給付のみでは、出産・育児休業後の職場復帰支援、保育所への入所措置などとの連携が弱いため、子育て全体の負担軽減にはつながりにくいであろう。
少子化による保育所不足や世帯構造の変化による家族内サポートの弱体化もあり、行政・育児サービス面の拡充も必要である。
女性の職場復帰後のキャリアパスの形成、働き方のフレキシブル化、企業による子育てサポートの拡充など企業と行政の連携も重要となってくる。
※記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 片山ゆき)