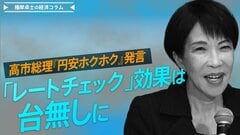育児手当をすでに実施している地域では継続も可能
中国では、これまで一部の地域で独自の育児手当が支給されてきた。
2024年10月時点で、育児手当を導入しているのは23地域(省・市・県など)で、多くは市レベルの実施にとどまっており、全国の都市の1割未満となっている。
多くの都市は2023年以降に導入しており、その背景には出産奨励策への転換となった「中国版エンゼルプラン」の発表がある。
支給内容や条件は地域によって大きく異なる。内容が公表されている10都市をみると、対象者は第3子が中心で、一部の地域では第2子も支給対象となっている。
第1子の支給は限定的であり、これは、第2子(2016年)、第3子(2021年)の出産容認・奨励の影響とみられる。
これに対し、今回の全国版の育児手当は出生順序に関係なく、第3子まで同額の支給を受けられるよう考慮されている。
支給条件は、多くの都市で両親の戸籍が申請地にあること(両方またはいずれか一方)を求めるなど、全国版より厳しくなっている。なお、所得制限などは設けられていない。
支給期間は多くの都市が3年間と全国版とほぼ同じであるが、支給額は全国版の年3,600元を上回るケースが多い。
例えば、本年6月に導入したフフホト市では、第1子から第3子まで支給対象とし、第3子は最長10年間支給するなど、長期かつ高額な制度を設けている地域もある。
中国政府は、既存の制度で全国版を上回る支給額を設定している地域について、上級の監督当局への届け出を条件に継続を認める方針を示している。
今後、若年層の移住促進などを目的とした育児手当拡充の動きも予想されるが、実施可能なのは財政基盤の比較的整った都市に限定されるとみられる。
地方財政の制約は依然として大きく、政府は育児手当支給に際して、省レベルの行政機関に市ごとの給付額に大きな格差が発生しないよう求めている。
加えて、これまで育児手当がなかった地域には新設を、全国版の支給額を下回る地域には引き上げを求めている。
ただし、0~3歳の平均養育費が73,614元(約151万円)であるのに対して、3歳まで支給される育児手当の総額は1人あたり10,800元(約22万円/全国版)となっている。
これでは出産直後の一部の経費を補うことはできても、育児の実質的な負担軽減効果は限定的と考えられる。