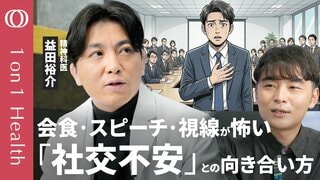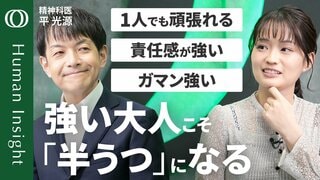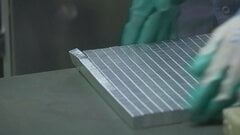学校教育と社会人教育でライフデザインを学び続けるために
こうした学習指導要領における高校家庭科の実効性を高め、Z世代が抱く将来の経済的な不安を解消するためには、いくつかの課題がある。
第一に、家庭科の単位数や履修の現状である。現行の高校学習指導要領では「家庭基礎」(2単位)または「家庭総合」(4単位)のいずれかの履修が必修となっているが、学校現場では前者が選択されるケースが多い。
この単位数では、膨大かつ変化する家庭科の学習内容すべてを十分に深く取り組むには授業時数が足りない。金融教育や社会保障、そしてライフデザインの探究までを網羅するとなると、知識習得にとどまらず、体験的な学びを通して「主体的に考える力」を養うにはさらなる時間的余裕が必要だ。
第二に、高校生及び保護者の家庭科に対する意識や価値付けの向上である。大学入試において家庭科は選択できない場合が多く、進路指導や学力評価の面で家庭科が「受験に直結しない教科」という認識は根強い。
いまだに「家庭科といえば調理や被服」というイメージにとどまりがちで、その学びの核心にある「ライフデザインの涵養」という本質まで意識が届きにくい現状があると考えられる。また、家庭科の授業内容が社会生活の基盤となりうることを十分に理解している保護者も多くないだろう。
第三に、教員の専門性や授業リソースの限界である。近年は金融経済教育や社会課題への対応として、家庭科教員にも高度なリテラシーや最新の知識などが求められているが、そのサポートは十分ではない。
教員は研究会などを通じて授業実践のアップデートを図っているものの、全てを専門的に指導するのは困難であるため、場合によっては外部から各分野の専門家を招聘することも必要である。
こうした課題を解決し、Z世代が将来的な経済不安を払拭できるようなライフデザインを学ぶ機会を一層充実させる方策としては、学校教育と社会人教育の両面から行うことが大切だ。
学校教育では、家庭科が「家庭」に直接関連する内容を学ぶだけではない科目となっている現状を踏まえ、「ライフデザイン科」に衣替えすることで、単位数や授業時数の充実を図ってはどうか。
すでに「家庭科」で行われているプロジェクト学習や体験学習、生徒同士・地域社会との協働活動を含めて、知識の習得にとどまらず「自分ごと」としてライフデザインを構築する意識や能力を醸成することが期待される。「ライフデザイン科」の履修は結果的に進路選択などにも資する可能性がある。
社会人教育では、前述のとおりZ世代前期(23~27歳)が、Z世代後期(18~22歳)に比べて「ライフデザインを学んだことはない」割合が高いことを受けて、「社会人になってからのライフデザインを学ぶ機会」を充実させる必要がある。現行の高校学習指導要領にもとづく文部科学省検定教科書の「家庭科」を読むと、社会人になってからも役に立つ内容が非常に多い。
むしろ、教科書に掲載されている「給与明細の読み方」や「住居の間取り」、「バランスのよい食生活に向けたレシピ」などは、社会人になってからこそ実感が湧くかも知れない。従業員のための「ライフデザイン研修」などを実施している企業も少なくないが、新入社員や若手社会人向けに、高校「家庭科」の教科書をもとにした研修(学び直し)を行うことも必要ではないだろうか。
このように、学校教育と社会人教育の両輪によって、誰もが必要な「生活人として自立し、よりよい人生を構築する力」を継続的に身に付けるとともに、Z世代を含む若者たちが将来の経済的な不安を払拭するために、ライフデザインを「自分ごと」として学び続ける機会を一層充実させることが求められる。
※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 西野偉彦)