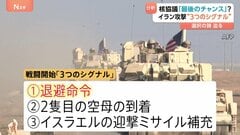隠れ待機児童の解消に向けて(1)企業
以上のように、待機児童がゼロになっても、実際には保育に関するニーズが十分に満たされていない現状がある。
隠れ待機児童の実態を正確に把握し、それに基づいた保育政策を一層推進すべきである。
ただ、保育士不足や就学前人口の減少に伴う今後の需要減を踏まえると、地域にもよるが単に保育施設を増やすことは得策とはいい切れない。
対策案として、まず、企業は努力義務とされているリモートワークの徹底が肝要だ。
対応できない職種もあるが、通勤時間がなくなることで保育園への送迎負荷は軽減される。
次に、育児休業を男女交代で計1年以上取得することも一案である。
現在男性の育休取得が進められているが、妻の育休中に同時に取ることが一般的である。
北欧などは夫婦が時期をずらして交代で取る。
日本においても、2022年の育児・介護休業法の改正により、休業期間の途中で夫婦が交代で取得することが可能となった。
このメリットは、キャリアブランクの短縮と保育士不足の解消だ。
現状、年度途中は保育園の空きが僅かで、4月の一斉入園のタイミングでの入園が大半である。
そのため、たとえば10月に出産した場合、生後半年あるいは1歳6カ月での入園を目指す人が多い。
1歳児クラスは0歳児よりも定員が少ない地域が多く、希望園への入園可能性を高めるには生後半年での入園を選択することとなる。
その場合、まだ子どもの生活リズムが安定しない時期に仕事を始めねばならず、両立の負担が大きい。
もっと長く子育てに専念したい人もいるだろう。
一方、1歳6カ月を選択すると、キャリアブランクが長くなる。
保育園が決まらない懸念も高まる。
仮に、妻が1年育休を取得し、その後に夫が6カ月取得すると、前者の課題および後者のキャリアブランクが緩和される。
さらに、0歳での入園を減らすことは保育士不足解消にもつながる。
保育士1人が受け持つ子どもの数は国が定めており、0歳児は保育士1人につき子ども3人、1・2歳児は6人までとされている。
上述のようなケースで、1歳以降の入園を選ぶ人が増えれば、保育士1人が担当する子どもの数が増える。
保育士不足による定員削減や新規園開設の遅延などの問題が軽減されるだろう。
このように男女が交代で育児休業を取得できるように、企業には、長期の男性育休の取得推進とともに、取得開始時期を幅広く選べるようにすることが求められる。