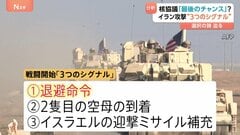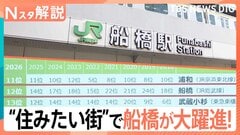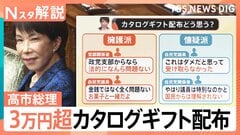「自慢」と「承認」 現代社会で空回りする遺伝子
ヒトの遺伝子に刻まれた特性の一つに「自慢したい」という欲求がありますが、「弥生格差革命(YKK)」以前は良い感情だったと小林教授は指摘します。
「『弥生格差革命(YKK)』以前は、大きな獲物を獲ったヒトは仲間に見せびらかすと、『よし、じゃあみんなで食べよう』という行動をとったのです。つまり自慢というのは喜びを分かち合うための感情だったのです」
しかし現代では、自慢の後に続いていた“おすそ分け”の要素が失われています。
個人の成功体験を聞かされても、聞き手には何の利益もないため、自慢は単なる不快な行為として受け取られがちです。
SNSでの承認欲求も同様の構造を持っており、表面的な承認は得られても、真の満足感や集団との絆の強化には至りません。
人間の“比べる能力”も、現代社会では逆効果です。
本来この能力は、集団内での自分の位置を把握し、適切な貢献レベルを維持するために獲得したものでした。
しかしSNSやインターネットの発展により比較対象が無限に拡大した現代では、この能力が絶え間ない劣等感や不満の源となっています。
「弥生時代まで、比べる能力はすごく重要でした。ただ今はその“比べる能力”が裏目に出ています。比べる対象が多すぎて努力しようというレベルではなくなり、諦めてしまうわけです。今はその能力のせいで幸せ感が減ってますよね」
テクノロジーで退化 ヒトとの関係を見直す時
人間のテクノロジーを創り出す能力も、幸福を阻害する要因の一つとなっています。
より良いものを求める「ベター思考」と「創造能力」は、人類がサバンナで生き残るために不可欠だったものですが、同時に新たな問題も生み出しています。
テクノロジーの根本的な問題は、その使用方法が遺伝子に刻まれていないことにあります。
「テクノロジーはヒトの役に立ちますが、使い方が難しいです。例えば釘を打つためにトンカチを発明したとします。でもトンカチだけを渡されたヒトは別のヒトを叩くかもしれないし、何か壊すために使うかもしれない。テクノロジーとは、作った本人は使い方を間違わないのですが、それを渡されただけのヒトは兵器にしてしまったり、マズい使い方をすることがあります。テクノロジーがどんどん大きくなればなるほど、収拾がつかないヤバさをヒトは引き起こすことがあるんです」
さらに現代人の身体能力の低下と満たされない承認欲求も、テクノロジー依存の弊害を示していると指摘します。
「100年ぐらい前まではヒトは50キロぐらい歩くことができたと言われておりますが、車や自動車といった道具やテクノロジーに頼って歩くことをやめたわけです。すると5キロぐらいしか歩けなくなりました。これも遺伝子と環境の不適合が起こっているんです。メンタル面でも集団から承認されないとか、自慢したら怒られるとかで幸せが感じられない。要するに現代社会と元々ヒトが持ってる遺伝子とのギャップみたいなことが起こって、ヒトだけが幸せになりにくくなっしまった」
そして特に懸念されるのは、AIの発達による思考能力の低下です。
「AIは少し怖いです。ヒトは考えることで生き残ってきたので、考えることをやめたときにヒトは絶滅に向かうと思っています。『AIが発展するとなくなる職業のリスト』が既にテクノロジーの使い方を間違えていて、AIに奪われる職業なんてありません。ヒトがやった方がいい職業、ヒトがやりたい職業は、ヒトがやればいいんです。それが道具の使い方なんです」
解決策「コミュニティの再構築」
これらの問題に対する解決策として小林教授は、災害が発生時を想定した現代的なコミュニティと、子育てや介護といった人生の重要なイベントを支援できるコミュニティの再構築の重要性を指摘します。
「子育てや介護というのは、人生の中で一番重要です。なぜならヒトの手がないとできないからです。いくらITが発展しても、SNSが発展しても、仮想空間ではどうにもならない。そのようなコミュニティを作って、人生において大きなイベントをサポートできるような集団を構築していくことが重要です」
また、社会全体として格差の固定化を防ぐ仕組みの構築の重要性も指摘します。
「格差が起こることはある程度しかたないと思います。でもその富の偏在が何世代にもわたるとか、あるいはその偏在が固定化されるというのはよくない。教育の機会は均等であるべきですし、稼ぎすぎてしまったヒトは社会に貢献する。その貢献で本当にそのヒトは社会に承認されるんだと思います。そういったような富の循環とか格差を是正するような仕組みをテクノロジーを使いながら構築していくことが重要だと思います」
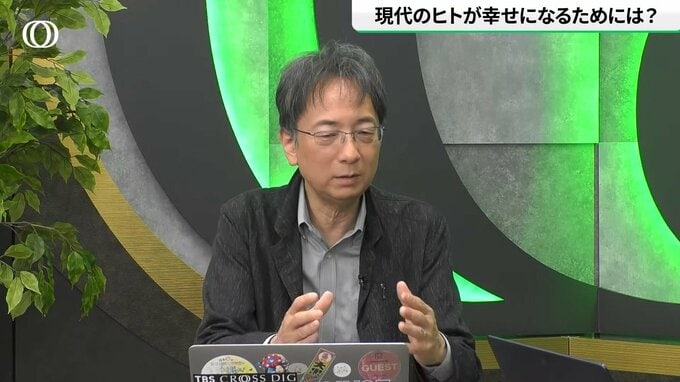
人間らしい幸福を実現するためには、700万年の進化で獲得した協力、正義、公平といった価値観を現代社会で活かせる仕組みを作ることが必要です。
小林教授は、テクノロジーの恩恵を受けながらも、人間の創造する喜びや自分で作り上げる満足感を損なわないテクノロジーの使い方を模索していくことが、真の幸福への道筋としています。
※この記事は6月11日にTBS CROSS DIG with Bloombergで配信した「Human Insight」の内容を抜粋したものです。