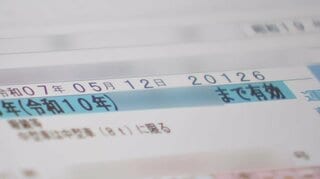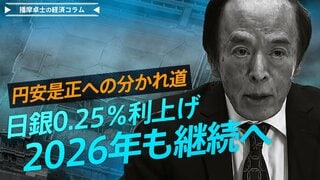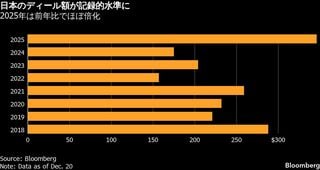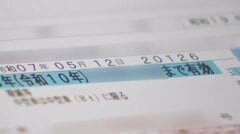(ブルームバーグ):トランプ米大統領の貿易戦争によって市場で緊張が続く中、投機筋や大半の投資家は円に対しては楽観的だ。しかし、円に対する強気な見方に抵抗を感じる人たちがいる。経済見通しを懸念する日本の富裕層だ。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントで日本地域最高投資責任者(CIO)を務める青木大樹氏は、日本の富裕層で上位に入る人々が1990年代初頭のバブル崩壊のトラウマをまだ引きずっていることが一因だと指摘する。富裕層が銀行に預ける多額の現金は、インフレによって日ごとに価値が目減りしている。
青木氏は東京にあるオフィスでインタビューに応じ、「景気の軟化や産業への投資不足によって1ドル=180円や200円の水準が現実味を帯びつつあると、富裕層顧客の多くが相当懸念している」と述べた。通商政策に関するトランプ氏の場当たり的な発言によって短期的な為替見通しは立てづらいが、「次の景気局面において」こうした水準に達する可能性はあるという。

円はここ数週間で下落し、トランプ大統領就任後に見られた上昇トレンドは反転した。関税交渉は先が読めず、トランプ氏の通商政策が世界の貿易にどう影響するのかも不透明だ。投資家はこうした現実に直面している。円は12日だけで2%余り急落し、150円台に迫った。米中が一時的に関税を引き下げたことで、ドルに対する弱気な見方が巻き戻されたためだ。
円が1ドル=180円台に急落し、200円に迫れば金融史に残るような水準となる。円が対ドルで最後に200円を付けたのは、プラザ合意翌年の1986年。円高が日本の輸出型経済に重しとなり、刺激策を促したが、これが結果的にバブルを助長した。1990年頃にバブルは崩壊。その後の数十年は株式投資家にとって厳しい時代だった。
株価指数はバブル崩壊前の水準に戻り、円は当時の水準まで下落しているが、バブル崩壊から数十年間における日本経済の変化こそが、富裕層を不安にさせている要因だ。
かつてはハイテク製品や自動車の輸出が止まらぬ勢いで成長し、経済超大国と見られていた日本は今や人口減少に直面。イノベーションの中心は米国や中国などに移った。日本では1990年代半ば以降、ほぼ一貫して物価が上がりにくい状況が続いたが、ここにきてインフレは上昇傾向にある。その一方で他の先進国のインフレは鈍化している。
懐疑的な富裕層
青木氏は「富裕層は日本経済に非常に懐疑的だ」と語り、イノベーションと人口増加がなければ、「日本経済全体を十分に支えられない」と続けた。
この状況を踏まえ、一部の顧客は外国資産の保有を徐々に拡大している。金が安全資産として注目される可能性もあるが、「状況の不安定さ」から、日本の投資家は「現金で保有する方が良いと感じるだろう」と青木氏は述べた。
野村総合研究所の報告書によると、日本の富裕層が保有する金融資産の割合は国外の富裕層と比べて少ない傾向にある。純資産額が1億円以上の富裕層世帯のうち、約70%は金融資産の保有額が5億円に満たなかった。一方、野村総研の野口幸司氏が2023年12月に発表した報告書では、世界の富裕層の57%が500万ドル(約7億3000万円)以上の金融資産を保有していた。
円が1ドル=180円まで下げるには、今週の約145円の水準から20%余り値下がりする必要がある。昨夏には2週間ほど160円を超える円安・ドル高が続いたが、それが外国の投資家や企業を刺激することはなかった。
青木氏は「160円の水準では、外国の投資家が日本市場に資金を投入する十分な要因にはならなかった」と指摘。「そのため、日本企業が国内に戻ってくるか、外国企業が日本への投資を拡大してインフラの整備を支援するまで、円はさらに下落する可能性がある」との見方を示した。
原題:Rich Japanese Still Fear a Yen Crash, UBS Wealth Manager Says(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.