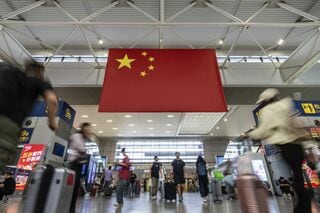(ブルームバーグ):ウォール街が新たな資産の宝庫を発掘している。日本の生命保険会社に積み立てられた保険金だ。米投資ファンドのKKRやアポロ・グローバル・マネジメント、その他の大手投資会社が管理する企業が、生命保険や年金保険を裏付けとする数十億ドルの運用に向け再保険契約を締結している。これにより、日本の保険各社は将来の保険金支払いに対する債務の一部を資産運用会社の保険部門に移転することでリスクを軽減している。
再保険契約において、元受保険会社は保険契約の管理と支払いの責任を負う一方、資産運用会社は債務を肩代わりすると同時に保険各社から多額の資産を受け取る。運用会社は、その資金を運用することにより、最終的に保険契約に基づく退職金や死亡給付金を支払う以上の利益を生み出すことができると見込んでいる。主要な投資先となるのは、現在最も注目されている高利回りのプライベートクレジットだ。
アジア第2位の経済大国であり、1億2400万人余りの人口を抱える日本は世界有数の保険市場の一つだ。生命保険協会によると、2023年度末時点での個人向け生命保険および年金保険の保有契約高合計は892兆8920億円に上る。KKRは日本の保険市場の約3兆ドル(約462兆円)が再保険の対象となり得ると推定しているが、現在の規模はその1%程度にすぎない。
アポロやKKRなどはプライベートエクイティー(PE、未公開株)ファンドとして知られているが、最近では大規模なクレジット事業も展開している。アポロが出資している保険会社アテネ・ホールディングやKKR傘下のグローバル・アトランティック・フィナンシャル・グループは長年、米国で再保険契約を手掛けてきたが、米保険市場での競争激化を受け、日本が魅力的な資金源として新たに浮上している。
PEファンドが関与している再保険会社が保険会社の生命保険契約の一部を引き受けると、それに基づく投資適格債などの資産を取得し、通常はそれらを売却して再投資する資金を確保する。資金の大部分(大抵は40-60%)は、関係のあるPEファンドが提供するプライベートクレジット投資に充てられる。これには企業への直接融資、トレードファイナンス、クレジットカード債権などが含まれる。残りは通常、債券などに投じられる。

一部の専門家はプライベートクレジット投資によりリスクが高まることを懸念しているが、資産運用会社は日本の保険契約者により良い機会をもたらす手助けをしていると主張している。
アポロのアジア太平洋地域責任者のマシュー・ミケリーニ氏は、再保険契約を締結する生保会社は保険契約の新規獲得やより利益率の高い新商品の提供に資本を振り向けることができると指摘。「再保険は単なる手段にすぎない。日本に安全な利回りをもたらす機会だ」と述べた。
日本では20年ぶりにインフレが起こりつつある。世界一の貯蓄大国である日本の家計は、現金および預金として1116兆円を蓄えてきた。政府は貯蓄を投資に振り向けるよう促してきたが、物価が上昇しないだけでなく、長年にわたり下落してきた時代においては貯蓄は安全な選択肢だった。
だが今、現金の価値は目減りしており、運用の性質を兼ね備える生命保険や将来の支払いが保証された年金保険が消費者にとってより魅力的になる可能性がある。ミケリーニ氏は、アポロの日本事業について「最大のチャンスは保険だ」と意気込んだ。アポロは22-24年にアジアで350億ドルを調達したが、その大半は日本からだった。
プライベート市場の資産運用会社は、日本の保険契約者の資産を再保険契約として吸い上げることに意欲的だ。なぜならそのような資金は顧客による引き出しが難しい、いわゆる「永久的な」もので、資産運用会社はそれを流動性の低い投資に利用できるからだ。
また、保険会社は再保険契約を活用することにより、債務のオフバランス化が可能となる。保険ブローカーサービス会社エーオンのアジア太平洋地域戦略・技術グループ責任者、ジョン・モーリー氏は、保険会社と資産運用会社の需要と供給が一致しているとの見解を示した。
ここ1年間において、投資会社の幹部らが日本を訪れ、日本の保険会社との提携に向けた意欲を表明している。昨年10月には、カナダの大手投資会社ブルックフィールドの関連会社が日本の再保険事業に参入し、新たな人材を責任者として採用した。
グローバル・アトランティックの共同社長マヌ・サリーン氏によると、KKRは再保険契約を通じてアジアで約110億ドルを調達しており、そのうち50億ドルは日本という。グローバル・アトランティックは東京に4人の従業員を配置し、資産獲得と新規保険事業に取り組んでいる。「これは、今後5年間の当社の成長にとって日本市場がどれほど重要であるかを示している」とサリーン氏は語る。
米投資会社ブラックストーンのスティーブン・シュワルツマン最高経営責任者(CEO)は、日本の保険会社と保険契約者にとって「非常に大きな」収益機会が生まれると述べる。しかし、運用資産1兆ドルを誇る同社は、自ら保険会社を所有して「顧客と競合する可能性」を受け入れるよりも、資産運用会社として保険会社と提携することを選好するという。
かんぽ生命保険で新規事業を統括する小川雄治関連事業室長は、再保険事業を展開するリインシュアランス・グループ・オブ・アメリカと再保険取引の契約を締結後、再保険に関する面談の依頼が増えたと説明。今後も再保険取引を行う可能性はあるとしつつ、緩やかな金利上昇がかんぽ生命の利益改善につながる中、再保険として出さなくても収益を確保しやすくなると述べた。
こうした中、PEファンドと関与している保険会社に対する規制当局の監視は強まっている。プライベートクレジット投資は流動性が低い傾向にあり、ファンドの急成長を巡る懸念のほか、深刻な景気後退やその他の予期せぬイベントが発生した場合に資産がどのようなパフォーマンスを示すかについても不安がくすぶる。
国際通貨基金(IMF)の23年の報告書では、PEファンドが関与している米保険会社は流動性が低い投資に対する資産の割合が同業他社よりも大きいケースが散見されると指摘されている。このようなケースでは、米保険会社が保険金の支払いに向け早急に現金が必要となり資産を投げ売りせざるを得なくなった場合、問題化する恐れがある。
モーニングスターのアナリスト、マイケル・マクダッド氏は「保険契約者としては不利になるわけではないが、このような傾向が続くと市場全体のリスクが高まる可能性がある」と警鐘を鳴らしている。
金融庁の幹部は、再保険契約の増加は流動性に関する問題を引き起こす可能性があるほか、保険会社と緊密に連携している投資会社との間で利益相反が生じる可能性もあると指摘している。同庁は発生し得る問題を注視していると同幹部は述べた。
一方で、再保険契約の追い風となる要因もある。25年に施行が予定されている日本の保険会社向け資本・会計規制では、保険会社は資産価値をより正確に反映することが求められる。これにより、超低金利時代のはるか前に販売した保険商品をオフバランス化する再保険契約の締結を検討する保険会社がさらに増える公算が大きい。
ブルームバーグ・インテリジェンスの保険アナリスト、スティーブン・ラム氏は「こうした保険商品の多くは1990年代に販売されたもので保証利率が高い。つまり基本的に毎年、これらの保険商品で損失が出ていることになる」と話した。
(原文は「ブルームバーグ・マーケッツ誌」に掲載)
原題:KKR, Apollo Tap $5.8 Trillion in Japan Life Insurance for Assets(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.