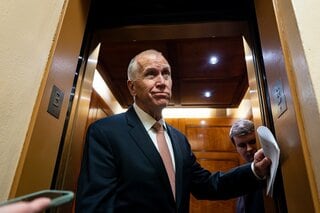2 社会減エリアは女性に選ばれにくいが、社会減のジェンダーレス化も
筆者が2018年から研究所レポートや講演会で主張してきたように、あいかわらず社会減エリアは男性よりも女性の方が多く減っているという状況に変わりはない。2024年も40社会減エリア中32エリア(80%)が男性よりも女性を多く減らす結果となっている。社会減40エリア平均(女性/男性が1.17倍)より大きな倍率となったのは17エリアである。
ここで注意しておきたいのは、片道の転入数、転出数で見れば男性の方が多いことである。一見、クラスの同級生単位で見ると、男性の方が多く地元から出ているために、男性の方が減っているという勘違いを体感しやすい。しかし、男性に関しては他のエリアからIターン移動してきたり、結局地元にUターンしてきたりする数が多い。女性は男性より出ていかないが、IターンUターンしてくる数が少ないために、結果として女性を多く地元から失うのである。簡単な式で示すと、
男性:200人出ていって、160人入ってくる 40人減
女性:140人出ていって、 80人入ってくる 60人減
といったイメージである。
社会減の男女アンバランス度合いでみると、栃木県が女性だけを1000人以上も減らすという女性に選ばれない県として際立っている。また、群馬県も男性の32倍という驚愕の男女アンバランスな女性減である。女性減が男性減の3倍を超えているのは熊本県、宮崎県で、2倍を超えているのは北海道、大分県となっている。このことから、北関東>九州>北海道の順で、女性減に強い危機意識を持つべきである。
一方、社会減数で男女数がほぼ同じとなるエリアも増加傾向となっている。別のレポートで解説するが、大学新卒を中心とした就職減が社会減の主たる要因であるため、令和時代のジェンダーレス価値観(多様性)教育を受けた若者が、男女関係なく地元を就職で選ばなくなってくる傾向も、今後拡大していくのではないかと考えている。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野馨南子)