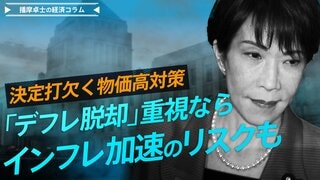(ブルームバーグ):日本銀行の田村直樹審議委員は6日、現在0.5%程度の政策金利を2025年度後半には少なくとも1%程度まで引き上げることが必要との見解を示した。長野県金融経済懇談会で講演し、その後に記者会見した。
田村氏は、不確実性はあるものの、25年度後半には2%の物価安定目標が実現したと判断できる状況になると展望。経済・物価に中立的な名目金利(中立金利)は最低でも1%程度との見方を改めて示し、「25年度後半に少なくとも1%程度まで短期金利を引き上げておくことが、物価上振れリスクを抑え、 物価安定の目標を持続的・安定的に達成する上で必要だ」と語った。

政策金利を0.75%に引き上げたとしても、実質金利は大幅マイナスだとし、経済を引き締める水準にはまだ距離があると説明。物価目標が実現する確度の高まりに応じて、適時かつ段階的に利上げを行い、「経済・物価の反応を丁寧に確認し、適切な短期金利の水準を探っていく必要がある」と述べた。
日銀は1月に昨年7月以来の利上げで政策金利を17年ぶりの0.5%程度とし、経済・物価が見通し通りに推移すれば利上げで金融緩和度合いを調整していく方針を維持した。田村氏は昨年12月会合で利上げを提案するなど政策委員9人の中で最もタカ派に位置付けられており、今回の講演でも政策正常化の継続に強い意欲を示した。
明治安田総合研究所の小玉祐一フェローチーフエコノミストは、田村氏の発言について「自らの見通しに一段と自信を深めていると思う」と指摘。米経済の下振れリスクは低下しており、賃上げムードも非常に良いとし、「基調的な物価上昇率にかなり上振れリスクが出てきているという見方が、政策委員全体のコンセンサスになりつつある可能性がある」と述べた。
午後の記者会見では次の利上げ時期については特段考えてないと言明。利上げペースに関しては、半年に1回などの予断は持っておらず、データや情報次第で早くなるか、遅くなる可能性もあると指摘した。25年度後半の1%程度への利上げを想定している中で、一定水準を念頭に置いた方が適時・段階的な調整が可能になると述べた。
物価目標の実現見通し時期を従来の26年度までの見通し期間の後半から25年度後半としたことについては、日銀の経済・物価見通しの実現確度が高まってきたと判断し、「前倒しというよりも、もう少し私の中で絞れてきたということだ」と説明。物価上振れリスクが顕在化した場合には、予想物価上昇率などの基調に反映される可能性があるとも指摘した。
田村氏の講演を受けて日銀の追加利上げ観測が高まり、外国為替市場の円相場は午前に一時1ドル=151円82銭と昨年12月12日以来の高値を更新した。その後は152円台前半での取引となっている。
ブルームバーグが1月の金融政策決定会合での利上げ後に実施したエコノミスト調査では、追加利上げ時期について最多の56%が7月の金融政策決定会合を挙げた。最高到達点(ターミナルレート)の予想中央値は1%だった。
多角的レビュー
田村氏は午前の講演では、消費者物価の動向について、人手不足による人件費の上昇とその価格転嫁を踏まえ、「上振れリスクが膨らんできている」と指摘。2%以上のインフレが3年近くも続く中で、日本人にとって重要な米価格の上昇もあり、「消費者マインドにダメージを与え、個人消費に悪影響を与えてしまわないか懸念している」と語った。
昨年12月会合で取りまとめた金融政策の多角的レビューに関しても見解を示した。黒田東彦前総裁が推し進めた大規模緩和はビジネスの新陳代謝の停滞によって生産性が低迷し、「供給サイドに対して大きな副作用があった可能性が高い」と言明。レビューにおける「全体としてみれば、わが国経済に対してプラスの影響をもたらした」との評価について、「言い切ることはできない」と主張した。
昨年9月の講演では、日銀が経済・物価情勢の展望(展望リポート)で示した26年度までの見通し期間の後半には少なくとも1%程度まで利上げする必要があると発言。12月会合では政策維持に唯一反対し、経済・物価が見通しに沿って推移する中、物価上振れリスクが膨らんでいるとして0.5%程度への利上げを提案した。
(田村氏の記者会見での発言を追加して更新しました)
--取材協力:氏兼敬子.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.