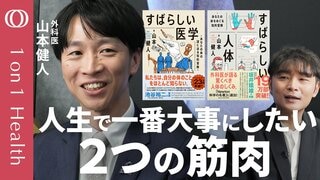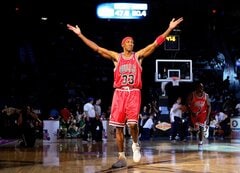卵子凍結のメリット・デメリット
今回は、卵子凍結の実態を東京都が取りまとめた調査結果から示したが、当然ながら卵子凍結にはメリット・デメリットが存在するため触れておきたい。
一般的な卵子凍結のメリットとしては、一番若い状態での卵子を保存できることに尽きる。将来いつ妊娠を希望するか分からない状態だと、少なからず現時点よりも老化した状態の卵子で授精することになる。卵子が若いと染色体異常や発育不良などのリスクが低くなり、希望したタイミングで妊娠をしやすくなることがメリットとして挙げられる。また、いつどのタイミングで疾患を発症するか事故にあうか、妊孕性の低下により不妊症の問題を抱えるか予見できないため、将来の保険としての意味合い(メリット)も持ち合わせている。さらに、近年、女性活躍促進やキャリア形成が推進されている社会情勢を踏まえ、妊娠のタイミングを調整することができる点も大きなメリットとなる。社会的卵子凍結が広まれば、今より自身のキャリアや生き方に応じて家族計画を積極的にコントロールしていくことが容易となるであろう。
一方で、デメリットも存在する。2024年時点で社会的卵子凍結については、保険適用外となるため全額自己負担となる。社会的卵子凍結に関する費用は、40万円以上50万円以上(35.0%)が最も多くの割合を占め、卵子凍結のための卵巣刺激や採卵自体は平均10万円を超過するのが一般的であり、費用負担は大きな壁となる。また、卵子凍結のために使用される排卵誘発剤は、過剰に卵巣を刺激するため、卵巣が腫れたり、腹水・胸水のリスクや、悪化すると腎機能不全や血栓症を引き起こすリスクがある。さらに、日本産科婦人科学会が発表した結果によると、2022年の凍結融解未授精卵を用いた治療成績として、移植あたりの妊娠率は20.9%と示されており、卵子凍結をしたとしても必ずしも高い治療成績(妊娠率)になるとは限らないことを認識しておく必要がある。
東京都では、社会的卵子凍結に伴う費用助成制度が存在しており、自己負担の軽減を図れるが、助成金を支給している自治体が限られていることや、居住エリア周辺に生殖補助医療機関がない、もしくは社会的卵子凍結を受け入れていない場合もあり、課題は山積している。今後、女性のキャリア支援や積極的に家族計画をコントロールするためのひとつの手段として社会的卵子凍結に対する支援の拡充が望まれるであろう。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛)