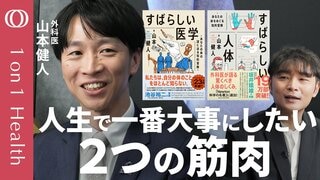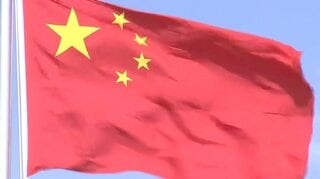キャリア自律には支援が必要
一人ひとりの意思をより尊重する人事異動が今後普及するならば、働く人びとには自身によるキャリア目標の設定が求められることになるだろう。働くということは、単に生活の糧を得る手段であるだけでなく、自身にとっての社会貢献や自己実現など働きがいにかかわる場合もある。それゆえ、働きがいを得るためにも、自分が大事にしたい価値観や希望を内省し、その結果をキャリア目標に反映させることが有効である。そして、その目標に対して不足している能力を見極め、いかにその能力を開発していくのか、自らプランニングすることが重要だ。
しかし、現状キャリアプランを自力で具体化できている労働者は多くない。そのため、キャリアの方向性を描く段階から企業や政策的な支援が必要なのではないか。たとえば、将来のキャリアを明確にするのに有効だと考えられるキャリアの専門家によるキャリアカウンセリングについては、それを希望する正社員は多いものの 、仕組みとして導入している企業は 1.8%(従業員 300 人以上の企業に限って も 4.4%)にとどまる。今後こうした支援策をより普及させていくことや、 研修や人事面談でも労働者自身の内省を促すような仕組みが求められるだろう。
また、厚生労働省の「キャリア形成・リスキリング推進事業」では、個人に対するキャリアコンサルティング機会を無料で提供している。過去の経歴や大事にしたい価値観を踏まえ、キャリアの方向性について専門家から助言を得ることができる。こうしたキャリア相談がより身近なものになっていけば、自らのキャリア目標を描く人も増えていくだろう。自分なりの目標をもち、そこに向けてスキル向上に取り組む人が増えるのは、企業や社会にとっても有益である。
キャリア自律は、働く人の主体性を重んじる考え方ではあるが、誰もが能動的に取り組めるわけではない。特に働きながら育児や介護等に従事する人にとっては、理想のキャリアと家庭との間で葛藤が生じやすく、目標設定や実際のキャリア形成が難しいこともある。今後は、そうした人びとも含めて一人ひとりがその人らしいキャリア目標を描き、納得感をもって能力開発していけるような支援が求められるのではないだろうか。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 副主任研究員 福澤 涼子)