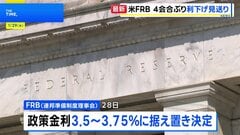人口減少社会だからこそ「海洋国家の防御優位性」と「人的損耗の縮減」を前面に
ここで、「人口減少」と「成長会計」を補助線に、自衛隊の在り方に関するナラティブを描いてみたい。人口減少社会だからこそ、貴重な人材の効果的な配置と人的被害の最小化が欠かせない。
キーワードは、「海洋国家の防御優位性」と「人的損耗の縮減」である。
(1)海洋国家の防御優位性
まず「海洋国家の防御優位性」について、海に囲まれていることをどのように評価するのかがポイントとなる。そもそも陸続きであったとしても攻撃する側は防衛する側の3倍の人員が必要との経験則も存在する。
さらに、日本の周りには広大な海が広がっていることに鑑みれば、海と空の防衛強化を図ることで上陸を防げる可能性は高まると考えられる。つまり、限られた人員のなかで、防御側であること、海に囲まれていることを戦略に活かすべきであろう。一方で、広範囲にわたる島嶼防衛の難しさや、狭い国土ゆえの縦深性の乏しさなどの課題も抱えている。
(2)人的損耗の縮減
次に「人的損耗の縮減」である。これには2つの側面があり、1つは人口減少のなかで今まで以上に「貴重な人材を失ってはならない」ということと、もう1つはそのような基本方針を示すことによる、自衛隊員募集に係る募集対象層への心理的効果である。
昨今の国際情勢においては、人的被害を厭わずに戦闘を継続する侵略者の恐ろしさと、国内で戦闘が行われることの悲惨さを目の当たりにしている。東西冷戦終結後にしばらく継続した平和な時代と、現下の国際情勢との間では、募集対象層の心理的なハードルに差があることは想像に難くない。
(3)2つのキーワード実現のための基本方針を持つこと
この2つのキーワードを実現するために「海と空の防衛強化によって上陸を許さない態勢づくり」と「徹底した省人化・機械化等により人的損耗を最小限に抑える」ことの重要性を強調したい。
前提条件として、陸を実効的に支配するには有人の部隊が必要で、実際に侵略を許した場合の最後の砦にもなることから、陸に貴重な人材を張る必要があることは押さえておかねばならない。現状においても定員の60.8%に当たる15万0,245人が陸上自衛隊である(2023年)。その上で、海と空の防衛強化を徹底するとすれば、対艦・対空防御、スタンド・オフ能力の強化などについて、少ない人員で最大の効果を得る方法を探ることとなる。
この際、成長会計において労働量減少局面で資本や全要素生産性を活かす発想に近しいが、徹底した省人化・機械化への投資、効果的な防衛に資するイノベーションを起こしていく必要があるだろう。
こうした基本方針を政府として明確化することは、入隊候補者の「有事の際に巻き込まれるリスク」をある程度払拭することにも役立つ。払拭できるほどの態勢が整うとすれば、それは上陸しづらい印象を相手国にも与えることにもなる。つまり抑止力の強化と表裏一体である。
災害派遣と自衛隊~自衛隊に頼る脆弱性、防災庁と人材の取り合いにならぬよう
最後に、今後顕在化する可能性がある課題として、自衛隊の災害派遣について私見を述べる。
地震や気候変動によって増加傾向にある豪雨などにおける自衛隊の活躍については誰しもが認めるところである。他方で、有事の際、自衛隊は本来の防衛任務に専念せざるを得ないことは自明であり、災害対応に十分な人員を割くことが困難となる。これは、平時において自衛隊の災害派遣への依存度が高い日本社会にとって、深刻な脆弱性を露呈させる可能性がある。
例えば、日本での大地震発生が、先ほど述べたFraud Triangleの視点における侵略国の「機会」になりうる、ということである。現在、緊急消防援助隊として、消防組織の広域化は進められてきているところである。2024年1月に発生した能登半島地震においても、自衛隊と比べてマスコミへの露出は多くなかった印象があるものの初動対応を含めて評価する向きは多い。実際、21都府県、2,000名規模の部隊が展開した。
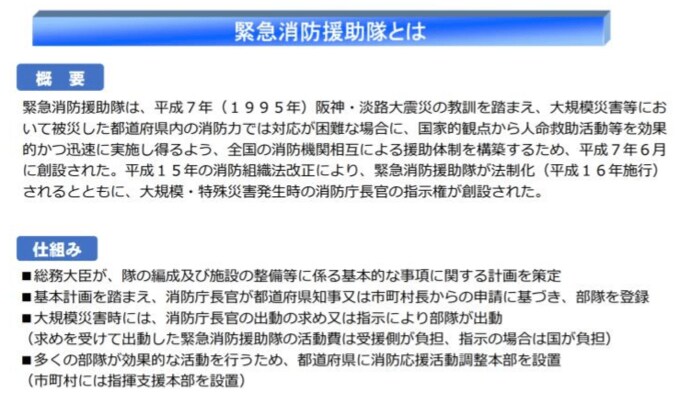
他方で、政府では「防災庁」構想を進めることとしている。防災への対応を国家レベルで強化していく、司令塔機能を強化していくことについて異論は少ないと思われる。ただし、新たに専任の災害対応部隊を作ることがもし俎上に載るとすれば、その是非や規模は慎重に検討した方がよいであろう。
自衛隊の隊員よりも災害専任職を希望する潜在募集対象層も想定され、人口減少下で自衛隊と新組織との間で人材の取り合いとなることは賢明ではない。厳しい安全保障環境の下で自衛隊の負担を減らすべく、評価が高い緊急消防援助隊を中心とした既存の体制を活かしつつ、司令塔機能、機動性、即応性をさらに強化・追求していくのが現実解であろう。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 取締役 総合調査部長 石附 賢実)