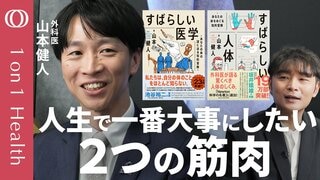自分の思いや願いを誰かに託して、その通りに実現してもらいたい、ということはよくあると思います。「忙しいので代わりに頼む」、「自分では出来ないので代わりにやってもらう」といった場合は、法律行為としては、「委任」することが一般的でしょう。ところが、「自分亡きあと、或いは、意思能力が低下してしまった後に、自分になり変わって何かをしてもらいたい。」という場合は、「委任」では、目的を充分達成できない可能性があります。
何故なら、「委任」が有効に成立するためには、自分(本人)が存在し、意思を表明できる状態であることが前提となっているからです。委任された者は、本人がいなくなってしまったら、一部の例外を除いて、その地位や権限は当然になくなると考えられています。
では、本人が存在しなくなっても、或いは、意思能力が低下してしまったときでも、「委任」と同じように法律的な権限と責任をもって、誰かに行動してもらうにはどうすればよいかというと、いくつか方法があります。例えば、本人が亡くなったあと、というケースでは、「信託」「遺言」などです。そして、意思能力の低下に備えて、という場合は、「任意後見」という制度が有効です。「任意後見」については、また別の機会に述べたいと思いますので、今回は「信託」と「遺言」について触れたいと思います。
「信託」では、上述の本人のことを委託者といい、「遺言」では遺言者といいます。そして、本人のために行動してくれる人(或いは法人)のことを、それぞれ、受託者、遺言執行者と呼びます。「委任」と違い、本人がいなくなってもきちんと行動してもらえるので、とても便利ですが、逆に、きちんと行動してもらえるだろうか、と不安になるのは当然です。
特に「信託」は、使い勝手がよく、さまざまな目的のために自由に設計することができるだけに、詳細に作り込まないと、受託者が、本来の目的に沿わない行動をしてしまう、或いは、判断がつかずに混乱してしまう可能性があります。ここで、少し長いですが、いかに信託がさまざまな目的のために使われているか、を現した文章をご紹介します。
「平和の夢が、商業的帝国主義が、競争を抑圧する企みが、楽園での共存への希求が、憎悪と慈悲が、死後を見越した家族への愛情かと思えば、びた一文も残すまいという怨恨が、あるいは礼装に包まれあるいは襤褸をまとい、ある者は尊い光背に照らされ、ある者はしてやったりとほくそ笑みながら、次から次へと通り過ぎる。信託はまるで(人それぞれに、ゆりかごから墓場まで、影もなく声もなく付き添う)守護の天使のようだ。」(※信託法の基本原理 デイヴィッド・ヘイトン著, 三菱信託銀行信託研究会訳 勁草書房)
これは、フランスの法律学者、ピエール・ルポール(Pierre Lepaulle)が、信託の無限の可能性について語った言葉と言われています。
近年増えてきた「家族信託(民事信託)」は、上述の中の「死後を見越した家族への愛情」から設定されるケースが多いと思いますが、受託者となる人は、信託や法律の専門家ではないことが多いと思われ、一層、きちんと作り込むことが重要となってきます。
「遺言」も同じようなことが言えます。せっかく遺言執行者に手続を任せたのに、いざ、執行手続きをしようとしても、どうすればいいのか分からなくなったり、手続を進められなくなってしまっては元も子もありません。また、遺言の内容によっては、相続人の間で争いがおき、場合によっては、そもそも遺言が有効なのか無効なのか、という裁判になることも珍しいことではありません。
そして、本人に、「実はどうなのか?」と聞きたくても、本人はいないのです。相続を巡りトラブルや、手続の長期化・放置の問題が増えてきたことから、政府も、遺言の普及に取り組んでいるのはご承知のとおりですが、遺言はとにかく遺せばよいかというと、必ずしもそうとは限りません。
特に、自筆証書遺言については、作成するときに、公正証書遺言の場合には存在する、公証人や証人がいないために、真贋を巡るトラブルになることもあるかもしれません。将来、トラブルや相続手続きを巡る混乱がおきないように人生を手仕舞うためには、自筆証書遺言であっても専門家に相談してみることをお勧めします。
ところで、アメリカのネイティブ・インディアンの言葉に次のようなものがあります。これからの高齢化社会、人生100年時代を考えるとき、この言葉のように人生を送るのは、なかなか簡単なことではなくなってきたと思いますが、少しでも近づけるようにしたいものです。
「あなたが生まれたとき、周りの人は笑って、あなたは泣いていたでしょう。だから、あなたが死ぬときは、あなたが笑って周りが泣くような人生を送りなさい。」
情報提供、記事執筆:MUFG相続研究所(三菱UFJ信託銀行) 所長 入江誠