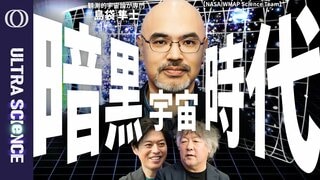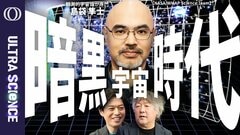タブー・トレードオフは、論理や理屈の面から対応することは難しい
そもそもタブーにはどういうものがあるのか。現在ペンシルバニア大学の心理学・政治学教授であるフィリップ・テトロック氏は、過去の著述(*2)のなかで、タブーを3分類して説明している。
(*2) “Thinking the unthinkable: Sacred values and taboo cognitions.” Tetlock, Philip E. (Trends in cognitive sciences, 7.7, 320-324., 2003)
1) 禁じられた基準率
物事の予測を行うために、ベイズ統計が行われることがある。ベイズ統計では、既に予測済みの確率を、新たな事象の発生という追加情報を用いて更新していくというスタイルで予測を進めていくものだ。
この予測を行うための基準率として、人間のグループについて一般化した確率を置くことがある。例えば、犯罪発生率の予測において、特定の人種や性別に対して、基準率を置く場合がある。しかし、その設定は人種差別や性差別を正当化することにつながる可能性があり、タブーとされることがある。
2) 異端視される反事実
歴史研究などにおいては、史実の因果関係について検討を行う際に、「反事実の仮定」を置くことがある。これは、「もし○○だったら、この史実はどう変わっていただろうか」といった検討である。
この反事実の仮定に、タブーが入り込むことがある。例えば、ある宗教で、「もし聖典が間違っていたら」とか「聖人の発した言葉が嘘だったとしたら」といった仮定を置くことが、これに相当する。こうした仮定は、当事者にとっては、それを置くこと自体がタブーとされる。
3) タブー・トレードオフ
宗教心や生命、生業などの神聖なものと、金銭やコスト、利便性など世俗的なものとの間で、どちらを優先するかを検討することを指す。
テトロック氏の説明によれば、タブー・トレードオフについては最終的に正しい判断がなされたとしても、熟慮して検討に一定の時間を要したこと自体が、人々の道徳的な怒りの対象になるとしている。
また、タブー・トレードオフは、社会を汚染していくという。タブー・トレードオフは非難せずにただ観察しているだけであっても、(当事者にとっては)タブーに加担していることになる。
このように、タブー・トレードオフは「タブー」という人間の心理に根差したものであるため、論理や理屈の面から対応していくことは難しい。
金銭で解決することは、人々のタブー・トレードオフの感情に火をつけることも
このタブー・トレードオフが、近年注目されるようになっている背景に、気候変動問題やエネルギー問題などの長期に渡る重大な問題を、経済などの合理性の面だけから解決しようとすることの課題が懸念されるようになったことが挙げられる。
心理学者でロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの教授のジェレミー・ギンジェス氏らが行ったイスラエルとパレスチナの紛争に関する2007年の研究(*3)によると、ヨルダン川西岸などの紛争地域の所有権や、パレスチナ難民が強制的に退去させられた村に戻る権利などの重要な問題に対してイスラエル人とパレスチナ人は、ある種の神聖な価値観を持っている。その価値観を妥協するために金銭を提供されることは、両者の怒りを呼び、問題解決への逆効果になるとしている(*4)。
(*3) “Sacred bounds on rational resolution of violent political conflict” Jeremy Ginges, Scott Atran, Douglas Medin, and Khalil Shikaki (PNAS, vol.104 no. 18, 7357–7360, 1 May 2007)
(*4) “The Psychology of the Taboo Trade-Off - Surprising insights into “sacred values,” and what they mean for negotiation”Adam Waytz (Scientific American, 9 March 2010)
また、2020年2月1日の日本経済新聞のコラム(*5)では、日本での原子力発電所の核廃棄物の地層処分(核廃棄物を加工したうえで地下深くに埋めること)の最終処分場選定にタブー・トレードオフの問題があるとしている。処分場を受け入れる住民は崇高な心に根差していると考えられるため、補助金の額を引き上げても誘致しようという気にはならない、と論じている。
(*5) 「タブー・トレードオフと地層処分」(日本経済新聞, 大機小機, 2020年2月1日)
こうしたことは、最近各地で起きている地震や台風などの自然災害の復興に伴う災害ボランティアについてもあてはまる(*6)。彼ら彼女らは、純粋にボランティア精神から、被災した人々を手助けしたいという気持ちで被災地に入っていると見られる。そうした純粋な奉仕の気持ちに対して、安易に日当を支給しようとすれば、かえって反発を招くかもしれない。
(*6) 「ボランティアにおけるタブー・トレードオフ 自尊心に打ち勝てる金額はいかほどか?」畑啓之(アルケミストの小部屋(ブログ), 2020.2.1)