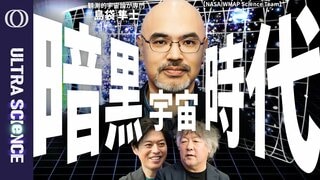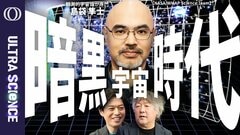人が日々活動をしていくと、さまざまなトレードオフに行き当たる。トレードオフとは、何かを達成しようとすると別の何かを犠牲にしなければならない、という関係を指す。つまり、両者は両立しえないこととなる。
いくつか例を挙げてみよう。大きなところでは、国の金融政策で、短期的な景気拡大と中長期的な経済成長の間のトレードオフ。環境政策で、経済発展と環境保護のトレードオフなどが問題とされやすい。
企業では、商品・サービスの品質と価格や、品質と納期のトレードオフ。経営判断におけるリスクとリターンや、リターンとコストのトレードオフなどが挙げられる。そもそも企業活動とは多くのトレードオフをさばいていく活動、と言っても過言ではないだろう。
個人のレベルでも、多くの人が、消費と貯蓄、キャリア形成と私生活の充実、健康維持と嗜好品の摂取(喫煙や飲酒)、活動時間と睡眠時間の確保等、さまざまなトレードオフを日常的に経験している。
トレードオフの中には、心理学で「タブー・トレードオフ」と言われる特殊なものもある。今回は、これを含めて、トレードオフへの対処について見ていこう。
トレードオフには3つのタイプがある
人が経験するトレードオフにはさまざまなものがある。ストックホルム大学ストックホルム・レジリエンス・センターの研究者を中心としたチームがまとめたペーパー(*1)によると、トレードオフは、そこに含まれる価値によって3つのタイプに分けられるという。
(*1) “Evaluating taboo trade-offs in ecosystems services and human well-being” Tim M. Daw, Sarah Coulthard, William W. L. Cheung, Katrina Brown, Caroline Abunge, Diego Galafassi, Garry D. Peterson, Tim R. McClanahan, Johnstone O. Omukoto, and Lydiah Muny (PNAS, vol.112, no. 22, 6949–6954, 2 June 2015)
1つ目は、金銭や利益といった世俗的な(secular)もの同士の「日常的な(routine)トレードオフ」だ。冒頭に挙げたさまざまなトレードオフの例が、これに相当する。この日常的なトレードオフには、釣り合わないような価値の衝突は含まれない。利益、コストや、そのパフォーマンスといった合理的な基準を設けて、それに基づいて評価や判断を行うことができる。
2つ目は、神聖な(sacred)もの同士の「悲劇的な(tragic)トレードオフ」だ。究極的な例として、医療現場で、2人の重症患者に対して1人分の薬剤しかない場合にどちらの患者に投与すべきか、といった状況が挙げられる。悲劇的なトレードオフには、評価が難しい事象や、重大な判断を要するものが含まれる。そのため、時間をかけて慎重に熟慮することが求められやすい。(ただし、災害医療における事故現場でのトリアージのように、短時間で判断を迫られるケースもある。)
3つ目は、神聖なものと世俗的なものの間の「タブー(taboo)・トレードオフ」だ。例えば、ある病院の経営で、医療費支払いに懸念がある困窮者の患者を治療するか、それとも病院の収益性確保を優先して治療を断るか、といった状況が考えられる。こうした状況は、公的医療保険制度が確立している日本では起こりにくいが、アメリカなどでは起きるケースがあると見られる。
タブー・トレードオフには、臓器移植を収益事業として行うこと、子どもの養子縁組の権利を斡旋売買することなどが含まれるとされる。人々は神聖な価値観を金銭と交換することを道徳的に嫌悪しがちであり、そのような提案に尻込みする。そればかりか、そうした提案を考えることにさえ嫌悪感を持つ状態になりやすいという。そのため、タブー・トレードオフの検討は、時間をかけてじっくり行われるのではなく、すぐに判断が下されがちとなる。タブー・トレードオフの判断においては、時間をかけないことが美徳とされる。