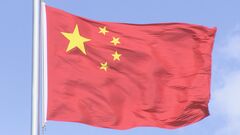電気自動車(EV)は、モーターのみを動力源(パワートレイン)とするため、モビリティの脱炭素化の切り札とされ世界で普及が進みつつあったが、昨年末以降世界需要が失速している。一方、エンジンとモーターをパワートレインに併せ持ちEVより手頃なハイブリッド車(HV)やプラグインハイブリッド車(PHV)が、再評価され需要が伸長している。
トヨタ社長「敵は炭素であり、内燃機関(エンジン)ではない」
EV失速の要因として、高価格、一部の国での購入補助金制度の終了、充電インフラの不足に加え、新しいもの好きの高所得層の「アーリー・アダプター」による購入一服などが挙げられている。これまでEVシフトを鮮明にしていた欧米の大手自動車メーカーは、足下の需要変調を受けて、EVよりもPHVやHVを優先する開発・販売体制へ転換しようとしている。
欧州連合(EU)を中心に、EV普及策が強力に推進されてきたが、EVを中心とするモビリティ社会の実現へ一足飛びに「瞬間移動」するのは難しいということが、足下のEV失速により露呈した。
そもそも現在のように発電用エネルギー(電源)のゼロエミッション化が、世界でまだ実現できていない段階では、エネルギー製造過程を含むライフサイクル全体でのCO2排出量で見ると、EVは必ずしも最適解とは限らず、PHVが最適解の場合もある。
2021年にトヨタ自動車の豊田章男社長(当時、現会長)は「カーボンニュートラルにおいて、私たちの敵は炭素であり、内燃機関(エンジン)ではない」と述べた。脱炭素化に向けた現実的な手段であれば、パワートレインは何でもよいという考え方であり、EV一択のように選択肢を狭めてしまうことへの強い危機感を持って発したメッセージだったという。この言葉を体現すべく、トヨタは得意のハイブリッドシステムに加え、EV、エンジン、水素、燃料電池といったパワートレインの多様な選択肢を全方位で準備する「マルチパスウェイ」の戦略を取ってきた。当時は世界的なEVシフトの流れの中、同社は「EVに出遅れている」と指摘されたが、マルチパスウェイは足下の市場変調を見事に先取りした卓越した戦略であったと高く評価できよう。
液化天然ガス(LNG)が争奪戦に
一方、エネルギー市場では、太陽光や風力などの再生可能エネルギー(以下、再エネ)の導入促進と化石燃料からの脱却による脱炭素化への取り組みが、世界的に活発化してきた。しかし、21年の天候不順による欧州での風力発電の不調に続き、ウクライナ紛争に端を発したエネルギー危機により、エネルギー安全保障の観点から、むしろ化石燃料の重要性が再認識される結果となった。特にCO2排出量が相対的に少ない液化天然ガス(LNG)の争奪戦が世界的に勃発する事態となった。これを受けて欧米の石油メジャーは、再エネより化石燃料の生産を優先する姿勢に転じている。
気候変動対策を主導してきたEUを中心に、再エネ導入の促進が世界的に図られてきたが、再エネ中心の電源構成の実現には、EVシフトと同様に一足飛びに進まないことが、21年以降の世界的なエネルギー需給ひっ迫により露呈した。