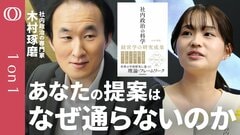(ブルームバーグ):日本銀行が7月30、31日に開いた金融政策決定会合では、政策委員から経済や物価の動向を見ながら、段階的に利上げを実施する必要があるとの意見が出た。「主な意見」を8日に公表した。
それによると、2025年度後半の物価安定目標の実現を前提に、「中立金利は最低でも1%程度とみている」との見解が示された。その上で、「急ピッチの利上げを避けるためには、経済・物価の反応を確認しつつ、適時かつ段階的に利上げしていく必要がある」との指摘があった。
利上げ後も「0.25%という名目金利は引き続き極めて緩和的な水準であり、経済をしっかりと支えていく姿勢に変わりはない」との認識も示された。このほか、「緩やかなペースの利上げは基調的な物価の上昇に応じて緩和の程度を調整するものであり、引き締め効果を持たない」との見方もあった。
会合では、17年ぶりだった3月会合以来となる今年2回目の利上げを決定した。主な意見からは、経済・物価が日銀の見通しに沿って推移していることに加え、物価の上振れリスクに対する警戒感が委員の間で強まっていたことがうかがえる。
一方で、「金融政策の正常化が自己目的になってはならず、今後の政策運営については、注意深く進めていく必要がある」との意見も出た。現時点では経済の持続的成長を裏付けるデータが少ないため、「次回会合で重要な経済データを点検して変更を判断すべきだ」との主張もあった。
植田和男総裁は会合後の記者会見で、経済・物価情勢が見通しに沿って推移すれば「引き続き金利を上げていく」とタカ派姿勢を示した。直後に米経済の後退懸念も強まり、世界的に株価が急落するなど金融市場は一気に不安定化。これを受けて、内田真一副総裁は7日の講演で「金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはない」と述べ、ハト派的な姿勢を明確にした。
追加利上げと同時に決めた国債買い入れの減額計画に関しては、市場に金利形成を委ねるため、「基本的には計画に沿って、国債買い入れの減額を淡々と進めていくべきである」との見解が示された。また、減額計画の目的はあくまでも市場領域の回復であるとし、「金融引き締めにあるのではない」との指摘も出た。
他の主な意見
- 足元の経済、極めて低い金利を幾分引き上げる程度に良い
- 前向きな企業行動の持続性確認なら、一段の緩和調整必要
- 現状は下振れ気味のデータ多く、より慎重に見極める必要
- 賃金と物価の好循環が働きだした、基調物価は2%へ着実な歩み
- 家計を中心に物価目標が従来より意識されていることを認識する必要
(詳細を追加して更新しました)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2024 Bloomberg L.P.