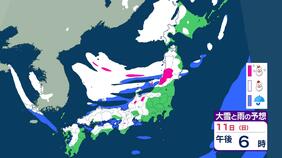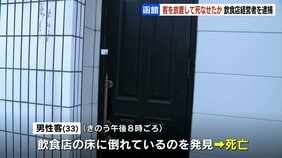最大震度6強を観測した5日の石川県能登地方の地震は、地震の規模、つまりエネルギーを示すマグニチュードが6.5でした。政府の地震調査委員会は能登地方の地震活動が「当分続くと考えられる」との見解ですが、富山や石川で地震の研究をする専門家は「本体の活動の前兆というか準備段階」としたうえで、今後マグニチュード7の可能性もありうると話します。マグニチュードが0.2上がると地震のエネルギーは2倍になり、0.5上がると5.6倍にもなるのです。心配される地震の今後について詳しく聞きました。

取材したのは富山や石川の地震の研究をする富山大学の竹内章名誉教授。富山大学理学部でテクトニクス(地殻の構造と運動)を専門に研究し、火山や活断層、山地の隆起 など現在進行中の地殻変動を物理地学の方法で調べるなど、将来予測に役立つ研究をされてきました。

記者:「ふたたび珠洲市で地震がありましたがどう見ていますか?」
竹内章名誉教授:「能登半島の北の海岸沿いで海のものも含めて地震帯というものがありますので、そこで起きているものだと思います。もう一つはそういう広い範囲のなかでの地震帯というほかに、珠洲で2020年の終わりぐらいからいろんな変動や異変が起きているんですけども、地面が盛り上がるとかそういうものと一緒に群発地震が続いてるんです。群発地震は3.11が終わって少し経ってからということで2016年ぐらいから始まってるんですけど急に増えだしたのは2020年の終わりぐらいから。これは2007年の能登半島地震の余震とは違っていて、珠洲の方で独立しておきているものなんです。その群発活動の一つだと思います」
記者:「2020年から能登で群発地震が相次いでいるのはどうしてですか?」
竹内章名誉教授:「群発地震が起きる仕組みから考えると地殻変動というような地盤の動きというか、そういうものが伴っていますので。そのあたりに群発地震の原因があると考えられる。近くの動きに関して言うと普通は地下からの水というものが考えられます。これは珠洲に限ったことではない。たとえば能登半島地震は2007年に起きているんですけどそのきっかけとなったのは水といわれています。それからもっと言えば富山の1858年の“飛越地震” (マグニチュード7.0 - 7.1と推定される地震)と呼ばれ、富山では有名な地震。これもきっかけは地下から深いところから上がってきた水がきっかけになって大きな地震になったというようなことで。その水に関係した地盤の動きが珠洲の場合は最近、観測機器が発達してきたこともあってデータが整ってきたので、非常にはっきりと見えたということだと思います」