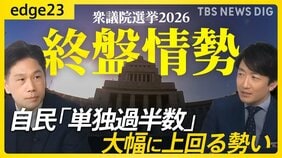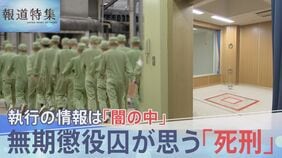小中高生の孤独に一歩寄り添うキャンペーンと題して、4月からの生活で悩んでいたり、孤独を感じていたりする小中高生に同じような経験をした著名人の方に当時の話や、いまになって思うことを4回シリーズで伺っています。最終回は不登校の経験があるという演出家の宮本亞門さんに、SBS『IPPO』の牧野克彦アナウンサーがお話を伺いました。
仏像が好きな高校生 日本の学校では個性が邪魔になる
牧野:宮本亞門さんというと、非常に気さく、かつ明るく、エネルギッシュなイメージがあるんですけども、不登校を経験なさっていたということなんですよね。
宮本:そうなんです。僕の場合は、実をいいますと、この明るさというのはあまりにも過去に暗い思い出があったということが影響しているということなんですね。高校生のときは1年間くらい不登校でした。最初は失恋がきっかけだったんですけども、自分が生きてる価値がないんじゃないかと、本当に恥ずかしながら自殺ばかり考えているようなときがありました。
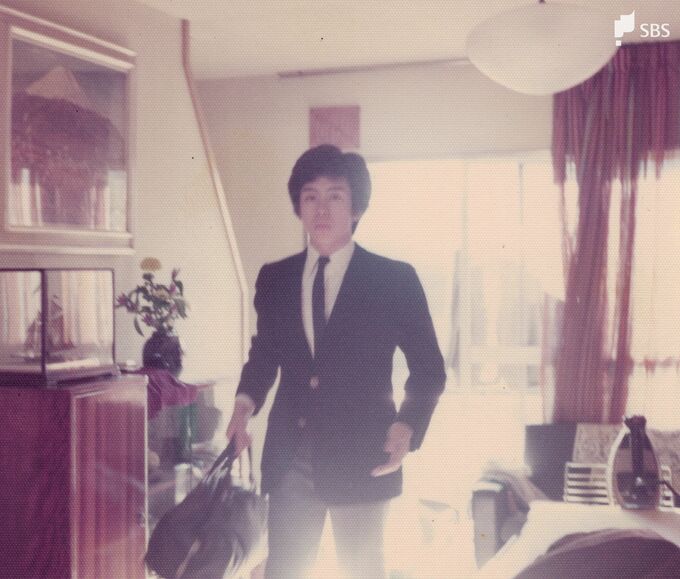
牧野:高校生のときということでしたけども、その前からそういう何か引きこもる前兆のようなものがあったのか、それとも、突然ひきこもりになったんですか。
宮本:元々子どものときから、ちょっと人と違うというか。例えば、みんなが「あのアイドルかわいいね」って学校で話題にしていても、自分はそこに別にあんまり興味ないのに一緒に同意して、何とかみんなに嫌われないようにしていたところから、だんだん違和感を感じていました。
私はその頃、お茶とか仏像とか、そういうものが好きだったんですけど、人に語れずに変人扱いされるというか、そういう意味ではちょっと変わった子と思われていただけに、人との交流が苦手だし、これ以上無理やり交流してもしょうがないという暗い子でした。
牧野:ある意味、個性的で非常に深みのある子どもだったのかなと思うんですけども、世の中の普通を求める雰囲気の中で、ちょっと引け目を感じられていたのですか?
宮本:やっぱり学校というのは授業をして、その授業による成績がいい子がみんなに認められるとか、違う考えを持っていることを面白いって、みんなで話し合うって時間がほとんどない。とにかく教えられることをこなすだけで、個性を生かすというよりは、むしろ個性があることが邪魔になっていたと感じていました。
僕は先生がこうだといっても「いや、ちょっと待って、本当はこういう考え方もあるんじゃないですか」って本当は話したいぐらいだったけど、そういう時間もなく進んでいくのが残念ながら日本の義務教育であると思うんですね。個性こそがその人のあり方っていうふうに世界が変わってきている中で、顔が見えないといわれてしまうのは、子どものときから自分の意見をどういうかっていうことを訓練されてないんじゃないかと僕は正直思ってます。