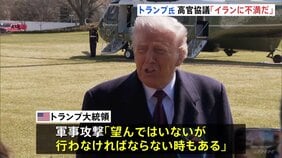寿命を「延ばそう」という考え方とは違う

野路:「寿命」のことを「天年」と呼んでいた時代は、命の長さはあらかじめ天から決められているもので、それを延ばそう延ばそうという考え方とは違うということですか?
磯野:「寿命を全うする」ということですね。いただいた恩を返していこうというイメージがかなり強いのが『養生訓』です。しかし今は、医学的な考えを基に、「親からもらった体をちゃんとしろ」なんて言うと、もはや人権侵害のレベルになってしまうかもしれないですが、行き過ぎさえしなければ、私はこの『養生訓』の中にある「養生観」、命の観念というのは、とても素敵なものだと思います。今は常に、医学の知識が生活にどんどん拡大している実感があります。
野路:磯野さんはコロナ禍に、介護施設でフィールドワークをされました。介護というのは、医学とはまた少し違うジャンルですよね。
磯野:そうですね。例えば、おじいちゃん、おばあちゃんがこれを食べたいなら食べさせてあげようという考えは、どちらかというと介護だと思います。乱暴な分類かもしれませんが、「いや、これを食べると誤嚥するかもしれない」「これを食べるとこんなリスクがあるかもしれない」と、“未来のために今を使う”考え方をするのが、現代の医学です。これはやはり統計学が入ってきたことが大きいと思います。
野路: 小野寺さん、身体的な健康を第一に考えることによって、幸福度や満足度を損なっているかもしれない。これが一つ、ウェルビーイングを考える時の観点かとも思うのですが?
小野寺:確かに、長生きすることがいいことなのかという話にもつながりますね。
今、医療にかかりたくないという人がほとんどです。薬だって飲みたくないにきまってるわけです。お酒が好きな人はお酒を飲みたい、タバコが好きな人はタバコも吸いたい。その方がよほど幸せだと思う人は当然いて、それ自体は否定されることではありません。医療はかなり押し付けがましいのですが、とはいっても、「こうしたら楽に生きられますよ」「タバコを吸うと病気になるリスクが高まるので、ちょっと我慢した方がいいんじゃないですか」と、ある程度自信を持って示せるくらいには、発展してきたと思います。『養生訓』にも、こうした方がいいよと書いてありますよね。
磯野:はい。「食べた後は300歩歩け」などと歩数まで書いてありますね。
小野寺:ただ、食べた後に300歩も歩きたくない、寝ていたいという人もいるわけですから、それは本人が選ぶことですね。そこに対する助言をしていくのが医療者の役目ですね。