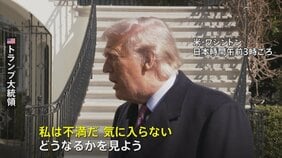新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府が国民に行動の自粛などを求めた緊急事態宣言から2025年4月で丸5年。新型コロナの感染症法上の位置付けは23年5月に「5類」に移行したものの、依然として厳しい面会制限を続ける医療機関や介護施設があるなど、コロナ禍の感染対策の影響は今も尾を引いている。
静岡県内唯一の第一種感染症指定医療機関として当初から患者を受け入れてきた静岡市立静岡病院は、国内でいち早く院内の感染対策の緩和に舵を切った。コロナ治療の最前線に立ちながら「通常の医療との両立」を掲げ、「余分な対策はやめる」という決断を重ねてきた。
同院の小野寺知哉理事長(前理事長兼病院長)がこのほど、医療人類学者の磯野真穂東京科学大教授と対談し、独自の決断の背景を振り返った。磯野教授は、コロナ禍になぜ行き過ぎた感染対策が行われ、多くの医療福祉現場でそれらをやめられなかったのかを考察した。進行はSBSの野路毅彦アナウンサー。
「病院に近寄るとうつる」と怖がられ 保育園が職員の子預かり拒否も
野路:静岡市立静岡病院は、コロナ禍でどんな役割を担いましたか?
小野寺:当院は静岡県でただ一つの、第一種感染症指定医療機関です。2020年2月、神奈川県からの依頼で、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の患者を受け入れたのが始まりでした。静岡県内で最初に、新型コロナに感染した患者の治療を担うことになりました。

野路:病院ではどんなことが起きましたか?
小野寺:まずマスコミが来て、なんとかして患者の写真や映像を撮ろうとしました。当院の職員がブルーシートで患者を隠しながら病室に運びました。その後、国内で感染が広がってきた頃から、当院に近寄るだけでコロナに感染してしまうんじゃないかと。それこそ半径500m以内に入るとコロナがうつるんじゃないかと。皆さんがすごく当院を怖がるようになりました。スタッフがタクシーを呼んでも「静岡病院へは行けません」と乗車を拒否されたり、スタッフが保育園から「子どもを登園させないでくれ」と保育を拒否されたりといった状況が、かなり続きました。
野路:2020年3月にはタレントの志村けんさんが、同年4月には俳優の岡江久美子さんがコロナに感染して亡くなった。元気に仕事をしていた方が、なすすべなく亡くなってしまう病気なんだと、我々は知りました。恐怖という感情を持つのは仕方がないことかもしれませんが、医学的には半径500m以内に近付いたから感染するというものでは、もちろんなかったですね。
小野寺:そうです。でも、最初は当然、皆さんにとって、コロナはやはり怖かったと思います。どんな病気なのか、うつったらどうなるのか、誰も分からなかったので。なんとかして感染から自分を守ろうとするのは、感情としては正しいでしょう。ただ、だんだんと、実は「それほど怖がるような病気ではないのではないか」ということが、少なくとも医療者はじわじわと分かってきましたよね。それなのに、初めの怖さがずっと、1年以上も続いたことについては、かなり問題があったと思っています。