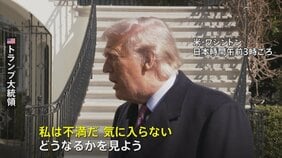医療の進歩に伴い、人々の「健康」や「ウェルビーイング」への関心が高まっている。新型コロナウイルスの感染防止のため、暮らしの営みの多くが「不要不急」として自粛を求められた緊急事態宣言の発令から2025年4月で丸5年。
『コロナ禍と出会い直す』著者の医療人類学者・磯野真穂東京科学大教授と、コロナ禍も全ての患者家族に寄り添う医療を提供し続けた静岡市立静岡病院の小野寺知哉理事長がこのほど対談した。
江戸時代の「養生観」から、現代の医療との向き合い方、医師との付き合い方まで、幸せに生きるためのヒントを探った。進行はSBSの野路毅彦アナウンサー。
野路:医療人類学では「健康」をどう捉えますか?
磯野:まず、健康という概念がいつごろ日本社会で生まれ、人々にどんな影響を及ぼしたのか、というところから考えます。昔から健康という概念があったわけではありません。江戸時代の医師で儒学者の貝原益軒が記した『養生訓』には、「健康」という言葉は1度も出てきません。「養生」という言葉は出てきますが、「健康」ではないんですね。歴史学者・鹿野政直さんの『健康観にみる近代』によると、「健康」という言葉が使われるようになったのは、遅くとも幕末からですが、幕末には庶民が広く使う言葉ではありませんでした。これほどまでに「健康」といわれるようになったのは明治以降だそうです。
『養生訓』に出てくる「養生」はもちろん、体を大切にしましょうという意味ですが、医学的な健康とは基本的な考え方が違う点が非常に面白い。『養生訓』に記されている、いわゆる「健康観」は、「孝」を尽くすために養生しなさいということです。あなたの命、あなたの体は、お父さんお母さん、そして天からいただいたものです。それに対して感謝を尽くすために、自分の体を大事にして、きちんと生きなさいといっているんです。
『養生訓』には、「天」という言葉が何度も出てきます。総論の上と下に分かれていますが、上だけで、100回以上も出てくるんです。そして、「寿命」ではなく「天年」と書かれています。「天から与えられた年を生きる」という考えに基づいています。
現代の医学書に、「天」という言葉はないでしょう。西洋医学が国内に広がるにつれて「天」という言葉は消えていきました。そしてこの体は人間がコントロールできるのだという考えが入ってきたのが、今の私たちが共通認識として持っている「健康」という概念だと、私は理解しています。