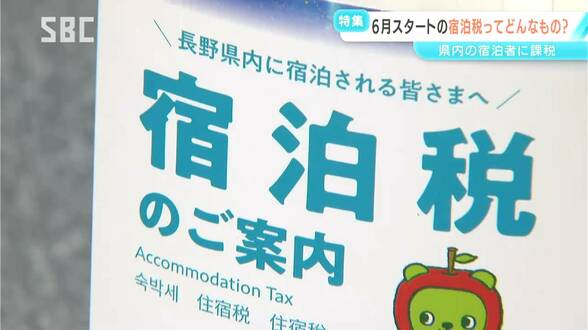国の統計調査によると、わさびのいわゆる芋の部分の生産量は、2022年の時点で長野県内はおよそ95トン。
栽培面積に大きな変化はないとされるものの、この10年でほぼ3分の1まで減少し、茎や葉を含めた全体の生産量も、4割以上減っています。
安曇野市農政課・竹岡江一係長:
「近年の異常気象であったり後継者不足。こういったものの関係で、生産量自体は減少傾向にあります。また病害虫による被害というのが深刻で、せっかく植えたわさびが、腐ってものにならないというような事象も起こっています」
こうした状況を受けて、安曇野市では2024年2月、『産地強化プロジェクト』を発足。
生産者やJA、県などが、栽培技術の向上や病害虫対策などに連携して取り組み、生産の安定を目指しています。
竹岡江一係長「市としては、今後も高品質なわさびの栽培生産農家にとって、後を継ぎたい、収益に繋がるような産業として育てていく。わさびといえば安曇野というのを、国内外に向けて発信していきたい」
一方、藤屋わさび農園では、さらなる輸出拡大を見据えて新しい工場を建設し、2022年から稼働させています。
望月啓市専務:
「3年目なんですが、新しい工場を作って、いま(生産量が)3倍くらいになっています。国内も中心に作ってるんですが、海外の方も、加工品の方も、生わさびと一緒に輸出をしています」
わさびを急速凍結し、真空パックにする装置も導入するなど、品質を長く保つ工夫により、コンビニや海外向けの商品も製造できるようになりました。
尾関アナウンサー:
「これからの夢は?」
望月啓市専務:「まだわさびが使われてない国にも使ってもらって、日本と言ったらわさびだよねと言ってもらえるような、代表的な食材にしていきたいなと思っています」
全国のトップニュース
【速報】韓国・尹錫悦前大統領に死刑求刑 内乱首謀の罪で

日韓首脳会談 対中国で連携は? 高市総理「両国が地域の安定のため連携を」 李大統領「両国が協力することはいつもより重要だ」 総理の地元・奈良で

【速報】吉村知事は「明後日の夕方までに結論考えたい」 大阪府知事・市長“出直し選挙”を検討 衆院選と同日実施の「トリプル選」か 「大阪都構想」住民投票の民意問う考え

【速報】東大阪の歯科医院で立てこもりか 40代とみられる男を確保 40代女性が灯油をかけられ目を負傷 東大阪市

事実上の号砲? “解散風”に翻弄される政治 通常国会23日召集も政府4演説の日程提示せず “解散検討”で野党反発 立憲は公明に選挙支援要請 選挙区調整は難航か

【訃報】久米宏さん(81)死去「大好きなサイダーを一気に飲んだあと旅立ちました」元日1月1日に肺がん 所属事務所が発表

金価格再び史上最高値更新 アメリカの金融政策の先行き懸念などから

「一時的に睡魔に襲われてしまった」通勤・通学ラッシュの時間帯にJR常磐線の運転士が“居眠り運転” 北千住駅手前で自動ブレーキ作動 駅の450メートル手前で停車