長野県内の公共交通のあり方を示す「地域公共交通計画」を検討する会議が開かれ、「自家用車に頼らなくても大きな不便を感じずに暮らせる社会の実現」といった将来像を盛り込んだ案が了承されました。
県や鉄道、バス、タクシーの事業者などでつくる協議会は、21日に長野市で開いた会合で、2024年度から5年間の「地域公共交通計画」について議論しました。
計画は「通院や通学、観光に必要な移動の保障」などの目標を掲げ、実現に向けた方策や、行政や事業者の役割分担を示すものです。
県内では運転手不足や新型コロナで拍車がかかった乗客の減少で、バスの減便が相次いでいます。
協議会の委員を務める専門家は、まずは行政と事業者が協力し、運転手を確保することが急務と指摘します。
名古屋大学大学院 加藤博和教授:
「バスは補助金が入っているが、そちらも人件費を高くするまでに至っていないので見直しが必要」
「(運転手は)公共交通担うには接客とかいろいろ知らなければいけない。ただ運転だけではだめ。いままでは個人や交通事業者の努力に頼ってきたが、地域で必要ならどう育てるか、学校のようなきちんと体系だったカリキュラムを作るとか、長野県なら早く実現して行かなければいけないのでは」
地域公共交通計画の案は、修正や住民からの意見募集を行った後、6月に策定される予定です。
協議会ではこのほか、JR東日本の交通系ICカード・スイカを、県内のバスや鉄道各社でも使えるようにする県の計画も了承されました。
全国のトップニュース
【速報】約4億2000万円入ったスーツケース奪われる 「お金を運ぶ仕事をしていた」 近くではひき逃げ事件も 警視庁が関連を捜査

【速報】羽田空港第3ターミナル駐車場で現金1億9000万円が入ったスーツケースを持った男性が3人組の男らから催涙スプレーをかけられる 男らは逃走中 警視庁

伊東市・田久保前市長が任意の事情聴取受ける 警察からの要請に応じる 学歴詐称疑惑で刑事告発=静岡

自民・単独過半数うかがう勢い 与党で「絶対安定」獲得か 中道は議席大幅に減らす見通し 参政・みらい比例で躍進 衆議院選挙JNN序盤情勢調査

続報 北海道せたな町沖で漁船「第28八重丸」不明 親子2組計4人と連絡取れず 漁船の木片が港に漂着か 転覆の可能性も

【“第2波”強烈寒波情報】30日(金)にかけて“1度目のピーク”迎える強烈寒波 “2度目のピーク”は2月2日頃? 気象庁の「全般気象情報」や「大雪などの予想シミュレーション」で見る最新予想は?
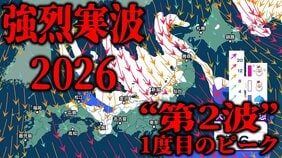
「銀歯1本で赤字6300円」貴金属高騰で歯科医が悲鳴 金1グラム3万円の影で“パラジウム”も高騰【Nスタ解説】
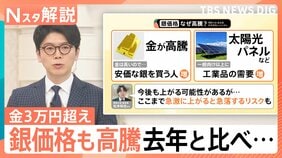
高い致死率「ニパウイルス」アジア各国で流行の懸念 ワクチン・特効薬なし…日本への流入リスクは?【Nスタ解説】





