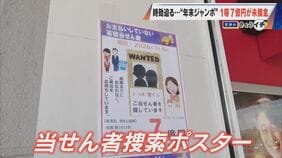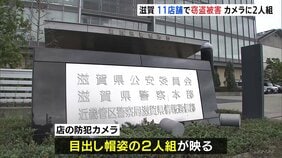建国記念「の」日となった理由
戦前の日本は、エキセントリックな宗教国家だったと言っていいと思います。日本歴史学協会の「声明」は、こう続いています。
「政府は、1966年、『国民の祝日に関する法律』を改訂して『建国記念の日』を制定し、政令によって戦前の『紀元節』と同じ2月11日を『建国記念の日』に決定して今日に至っている。私たちは、政府のこのような動きが、科学的で自由な歴史研究と、それを踏まえるべき歴史教育を困難にすることを憂慮し、これまで重ねて私たちの立場を表明してきた。(中略)歴史学はあくまで事実に基づいた歴史認識を深めることを目的とする学問であり、歴史教育もその成果を踏まえて行われるべきであって、政治や行政の介入により歪められてはならないことを主張するものである」
非常に大事なのですが、「戦前の反省に立っている」ということです。歴史学者の反対を押し切り、1967年に「建国記念の日」が祝われた。私の生まれた年なんです。そのころに「紀元節の復活ではないか」と大論争になっていたわけです。ただし、「建国記念日」、さすがに「日本ができたその日である」とは言い切れなかった。「建国記念の日」と、一歩引いた形になったのです。
「紀元節」「大東亜戦争」「八紘一宇」……。戦争では300万人以上の死者が出ました。超国家主義がどんなことをもたらしたか。それははっきりしているので、戦前の超国家主義が使ったこうした言葉を安易に使わないようにしよう、いうのが戦後日本の立場だったのですが、保守派が「紀元節を復活させなければならない」と言う中、妥協の産物がこの「建国記念の日」なのです。たった一文字、「の」がどうして入ったのか。2月11日は、どういう日なのか。考えるのにはいいかなと思ったので、今日は古い新聞を持ってきました。

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年生まれ。学生時代は日本史学を専攻(社会思想史、ファシズム史など)。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。東京社会部での勤務後、RKBに転職。やまゆり園事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー映画『リリアンの揺りかご』(2024年)は各種プラットフォームでレンタル視聴可。ドキュメンタリーの最新作『一緒に住んだら、もう家族~「子どもの村」の一軒家~』(2025年、ラジオ)はポッドキャストで無料公開中。