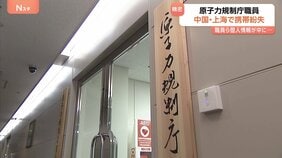沖縄本島の北部に位置する名護市久志区。ここには正月早々、十字に組んだ丸太に男性がまたがり、股間を刺激しながら地域を練り歩く伝統行事があります。なぜ男たちは激しい痛みを受けながらも伝統行事に臨んでいるのでしょうか。
「痛い、怖い」なぜ男たちは丸太にまたがるのか
「恐怖心はありますよ、いままで乗った人たちの話を聞くと…」

緊張した面持ちで、その時を待つ男性。この日の主役・比嘉泰仁さんです。十字に組まれた丸太にまたがり、3人の男性がその丸太を担ぎあげます。
「ドウドイ、ドウドイ。ドウドイ、ドウドイ」
太鼓やほら貝の音と共に、ドウドイという謎の言葉を発しながら集落を練り歩く集団。派手に揺れる丸太にまたがる比嘉さんは、苦痛の表情を浮かべます。

これは沖縄県名護市の久志区で行われる伝統行事「ドウドイ」。巷では日本の奇祭の1つとも言われています。
男性がまたがる丸太に使われているのは、集落に自生するアダンの木。幹にある無数の棘がこれまで数々の男性を苦しめてきました。
地域の歴史に詳しい 宮里健一郎さん(2023年取材)
「子宝に恵まれますようにとか、そういう願いも含めてやられた行事ですね」
「このゴツゴツが直に男性のアソコを刺激する。とにかく股間が痛いとだから、効くんだよと。いつから始まったかということは誰も分からない。現在もいつから始まったかということはわかっていません」

子宝を願って行われるもドウドイ。2011年から取材を続けてきたRBCの記録を見返すと、父親がドウドイを乗った後に誕生し、自らドウドイに挑戦する男性や、ドウドイによって子どもを授かったことで2度目の挑戦をする男性など、地元の人たちはそのご利益を実感していました。