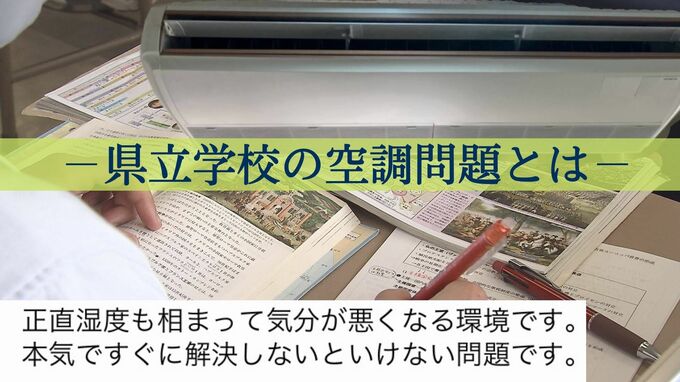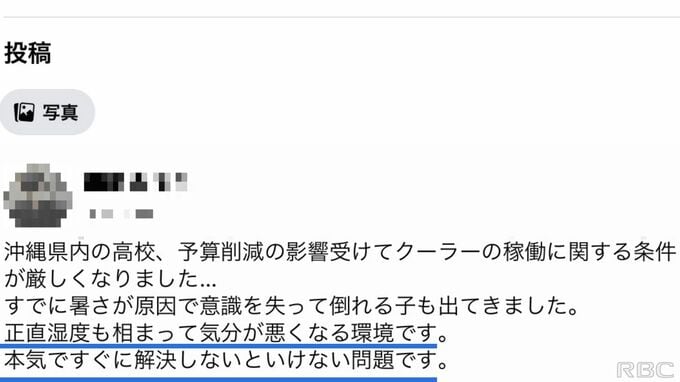
「沖縄県内の高校、予算削減の影響を受けてクーラーの稼働に関する条件が厳しくなりました…、湿度も相まって気分が悪くなる環境、本気ですぐに解決しないといけない」
これは県内の高校生が先月16日にSNSに投稿した内容で、学校内の空調に関する問題を指摘しました。高校生は同世代に対して空調環境に関するアンケートを呼び掛け、800件近い回答のうち、「勉強に集中できない」「熱中症になりそう」など、暑さで授業に集中できない、学びの環境として適切とは言い難い状況にある意見が多く見られました。
文科省が定める基準では教室の室温は「室温は18℃以上、28℃以下が望ましい」としていて、これに対して県教育委員会は2016年から「一年を通して室温が27℃を超える場合に冷房を稼働」「光熱水費の予算が超過しないよう教職員、生徒一体となって節減すること」と基準を定め、ことしも同様の条件で対応していると話していて、現時点で学校での暑さによる熱中症の報告などはあがってきていないとしています。
しかし生徒たちに話を聞くと…
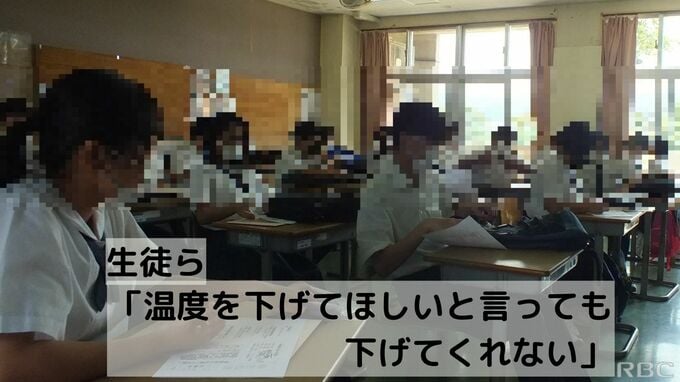
「暑すぎて倒れそうになったことがある」
「温度を下げてほしいといっても、下げてくれない、汗だくになる」
この学校の空調をめぐる現状について県議会でも質問が相次ぎました。
島袋大議員
「県立高校のクーラーの稼働時間について時間設定もろもろを含めて稼働していない時間があると、0校時、自習時間、放課後などクーラーが入れられていないということへの対応は?」

半嶺満教育長
「勤務時間外は原則認めていない、早朝講座は柔軟に対応している認識だが、電気料金の価格高騰などがあり、各学校に対して柔軟に対応するよう通知している。生徒の健康問題にかかわるので適切に対応したい」
6年前から同様な条件でクーラーは稼働させているものの、なぜ学習環境が悪化してしまっているのか? この問題には新型コロナも大きく関わっています。学校内では感染予防で常にマスクを着用することに加えて、窓を開けて換気を行うなどの対応を講じています。クーラーを稼働させても冷気が逃げてしまい、涼しさを保っているとは言い難いといいます。
教諭らに話を聞くと「連日真夏日が続く上に、特に湿度の高い沖縄ではクーラーを稼働させても教室が蒸し暑い状態となるケースも少なくない」と話していて、「更に温度を下げてあげたいが、勝手に判断することが難しい」として、生徒に我慢を強いてしまうこともあると話しています。
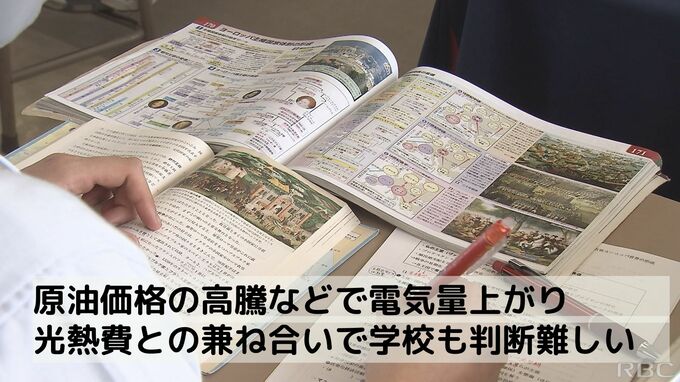
クーラーを稼働させる権限は各学校長に委ねられていて、県から振り分けられた光熱費の範囲で運用しないといけません。しかし原油価格の高騰やロシアのウクライナ侵攻などに伴う電気料の高騰などの背景があり、学校側も難しい判断を強いられているといいます。
県は空調の稼働に関する調査を実施していて、「予算を理由に冷房の使用を制限することのないよう対策を考えたい」としていて、梅雨が明け、連日真夏日が続く中、子どもたちの学びの環境をどう守るのか、対策を急ぐ必要があります。