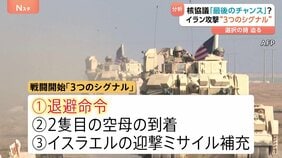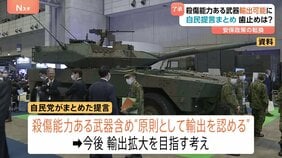大雨や台風によりこの夏、大分県内各地で相次ぎ発生した土砂災害。なぜ起きたのか?大分大学減災・復興デザイン教育研究センターが調査した結果について明らかにしました。
由布市で起きた「土砂崩れ」数年前から崩れた形跡が…
(高橋宏明記者)「湯布院で男性1人が亡くなった土砂崩れが発生してまもなく2か月なりますが、現地では災害の爪痕が今なお残されています」

6月30日夜、由布市湯布院町で土砂崩れが発生。住宅1棟が巻き込まれこの家に住む70歳の男性が亡くなりました。当時、由布市には観測史上最大となる1時間に68ミリの非常に激しい雨が降りました。
災害からまもなく2か月となりますが、現地は流れ出た土砂で今も通行止めとなっていて土砂の成分などを調べる地質調査が進められています。大分土木事務所によりますと、9月中旬まで調査を続け、早ければ年明けに土砂の撤去作業に入る見込みということです。
ここで生まれ育ち、現場近くに住んでいる八川和夫さんは家が押し流される土砂災害は初めての経験だったと振り返ります。
(八川和夫さん)「今までにない雨量だった。あそこがあんな風に崩れるなんて予想していなかったからですね。やっぱりどこでも起こりうるというような感じを受けました」
今回、災害が起きた現場の地形について専門家は山に窪んだ場所があり、雨が集中しやすい状況が生まれ、その結果斜面が大きく滑り落ちる「地すべり」が発生したと指摘します。
大分大学減災・復興デザイン教育研究センター 鶴成悦久センター長:
「どちらかというと、ここは弱層といって少し緩くなっている可能性がある。そこに雨水が集中、背後地に波及して崩れてきたという現象です」

このエリアは数年前から崩れた形跡があり、比較的柔らかい地層だったということです。そこに記録的な大雨が降り、地すべりの発生につながったとみられます。