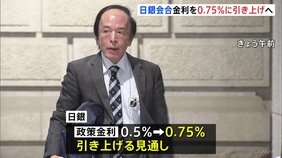「訪問介護」持続の可能性は?
こうした中、65歳以上の高齢者同士で介護しあう「老老介護」が、家庭内だけでなく訪問介護の現場でも起きています。妻と息子2人に先立たれた安東俊治さん(92)は、足が不自由で、去年から調理や買い物の支援を受けています。安東さんは、長年住み慣れた家で暮らし続けるためには「訪問介護がないと困る」と話します。

(安東さん)「制度があるから楽じゃわ安心じゃわ。動き切らんことになったら無理を言うて施設に行くか…。1人でじっとしちょれんわ」
訪問介護事業者の倒産、休廃業・解散は去年、全国で過去最多の529件にのぼり、10年前から3倍に増えています。人手不足に加え、国が昨年度から訪問介護の報酬を引き下げたことが要因とされています。

左右知新一常務理事:
「人材不足の現状の中で、一事業所としてはなかなか問題解決ができない。経営の方も非常に厳しい状況になっています」
県では今年度、経験の浅いヘルパーにベテランが同行する取り組みに補助金を出す新規事業を打ち出しました。また、11月には介護職の魅力を発信するイベントを初めて開催します。
県高齢者福祉課 渡辺康弘課長:
「国の方向性もありますが、県としても独自にいろんな取り組みをしていかないといけない。訪問介護に関しては特別に手厚くしていきたいと考えています」
ホームヘルパーの佐藤さんは、自身も後期高齢者に近づいていますが、それでも働き続けるのは、介護という仕事にやりがいや誇りを持っているからに他なりません。

佐藤さん:
「夏場は汗でびっしょりになるし、追い返されることもありますが、利用者が喜んでもらえたらうれしいし、仕事が好きだから続けています。今のところ75歳まで続けますが、それでもまだ元気だったらやっているかもしれません」
住み慣れた自宅で暮らし続けたい――その思いを支える訪問介護。誰もが平等に受けられるサービスの持続に向けて抜本的な対策が急がれています。