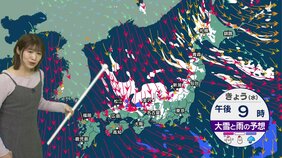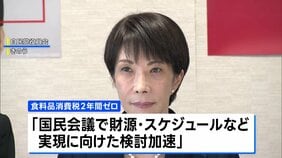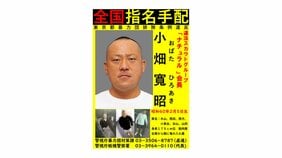火葬場が不足…遺体袋に入れて仮埋葬しかない
県歯科医師会の木村哲也専務理事は東日本大震災の時、1週間で31人の身元確認作業に従事。毎日運ばれてくる多数の遺体を遺族に引き渡すために安置所の重要性を訴えます。
県歯科医師会 木村哲也専務理事:
「東日本大震災では、はじめのうちは遺体が1日で1000体あがったと言われていて、遺体安置所の外側にはテントがたくさんあった。私がいたときもあったんですけど、そのテントの中でも遺体の収容や身元確認の作業をやっていた」

「安置所では医師が遺体の検案書を作成するために死因の特定をやります。それが終わったあとに歯科医が身元確認作業をやります。それが終わった遺体が移動し、棺桶で入っていくことになる。なるべく大きな安置所をかなりの数を用意し、いざとなればここを使うと決めておいた方がいい」
遺体安置所は雨風をしのげる広いスペースが必要ですが、災害時に用途が決まっている公共施設が多く、遺体を扱う忌避感から議論を進めにくい実情もあります。
佐伯市にある3か所の火葬場では1日の最大処理能力が12人。8745人の遺体を火葬するにはおよそ2年かかる計算です。市は県外を含めた広域火葬を計画していますが、身元がわからない遺体は一時的に土葬せざるを得ないとしています。
佐伯市防災危機管理課 増田響さん:
「遺体の安置所は災害発生時に遺体を全て収容できるほど確保できていないため、現在選定をしております」
課題が山積するなか、去年11月に行われた県の総合防災訓練では初めて遺体の安置訓練が実施されました。県や佐伯市をはじめ、関係機関が連携を深め、浮き彫りになった課題の解決に向けて本格的に動き出しました。

県防災対策企画課 後藤恒爾課長:
「最大規模で被災した場合は遺体袋に入れて仮埋葬するという形でしかない。そうした非常に悲惨な状況になるだろう。早期の避難ができれば2万人の死者を600人まで減らすことができる。日頃から地震が起こった時には津波を想定して、まずどこに逃げるかを決めておいて、どのように逃げるか、どういうルートで逃げるか決めておくことが鍵になる」
犠牲者の尊厳をどう守るのか――遺体管理に関する対策を急ぐとともに、最悪の事態を回避するため、自分の命は自分で守る一人ひとりの備えも必要です。