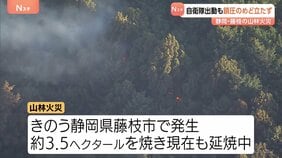事故などで脳に損傷を負うことにより発症し、「見えない障害」とも言われる高次脳機能障害についてです。
宮崎県議会の常任委員会で高次脳機能障害の当事者や家族が支援体制の整備を訴えました。
17日、開かれた県議会厚生常任委員会には、「みやざき高次脳機能障がい家族会あかり」のメンバー6人が出席しました。
病気や事故で脳が損傷することで発症する高次脳機能障害は、集中力が続かない「注意障害」や新しい出来事が覚えられない「記憶障害」などの症状がありますが、外見からはその障害が分かりにくいため、「見えない障害」とも言われています。
家族会のメンバーは議員との意見交換で、県指定の支援拠点に障害のレベルや特性を評価できる専門家がいないことや、特性に応じてリハビリを受けられる施設が県内にほとんどないことなど現状を伝えました。
(高次脳機能障害の当事者 二見一明さん)
「見えない障害って本当につらい。こういう実態があるんだよということを行政の方が理解していただいて、何かの形でサポートしていただけるような県政にお願いをしたい」
(みやざき高次脳機能障がい家族会 あかり 飛田 洋 会長)
「長期間でやれるような、ちゃんとした事業所を設けること、そして、専門スタッフがそれに携われること、そして、医療がそれと繋がりながら、ずっとフォローできること、そんなことを急ぎ作らないと、いつまでたっても改善できないと思います」
県が昨年度行った実態調査によると、県内で高次脳機能障害と診断された人や疑いのある人は、少なくとも7000人余りに上ると推計されています。
県議会厚生常任委員会は、今後も家族会との意見交換を続け、委員会や調査活動に反映させていきたいとしています。