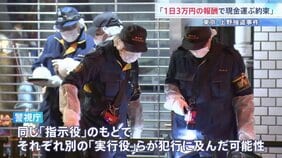多彩な方言が物語る日本の言語文化の豊かさ
メバルとカサゴは見た目が似ているため、同じ名前で呼んでいる地域がある。例えば、北陸三県でメバルの代表的呼び名だったハチメは、同じ北陸でカサゴの呼び名としても使われている。同様に、メバルの呼び名として和歌山から四国沿岸部に分布するガシラも、同じ地域でカサゴの呼び名としても使われている。
このように種類の違う魚を同じ呼び名で呼んでいることは、その地域の人々が両者を同じ魚だと認識していた可能性を示している。
これに似た現象は他の方言でも見られることがある。例えば、白山ろくの白峰方言では、昼に出て血を吸う蚋(ぶよ・ぶゆ)をカーメ、夜に出て血を吸う蚊をヨガメと呼んでいた。これは白峰の人たちが蚋と蚊を、血を吸う同じ蚊の仲間と考え、出現する時間帯で区別していたことを教えてくれる。
メバルの呼び名の全国的な地域差を概観すると、実に多彩な呼び名が存在することがわかる。そして興味深いことに、こうした方言の研究は、単なる言葉の地域差にとどまらず、人々の生活や自然との関わり方、自由な名付けの発想、魚の種類の認識の仕方にまで光を当てることにもだろう。標準和名のメバルや北陸のハチメなどを除くと、多くの方言名はその由来が不明というのもこの魚の特徴だ。
これらの多様な方言名は、各地域の人々が魚とどのように関わり、どのような特徴に注目してきたかを示す貴重な言語文化の証である。日本海から太平洋まで、北海道から九州沖縄まで、同じ魚を指す呼び名が驚くほど多様に存在した事実は、日本の言語文化の豊かさを物語るものでもある。
加藤和夫
福井県生まれ。言語学者。金沢大学名誉教授。北陸の方言について長年研究。MROラジオ あさダッシュ!内コーナー「ねたのたね」で、方言や日本語に関する様々な話題を発信している。
※MROラジオ「あさダッシュ!」コーナー「ねたのたね」より再構成