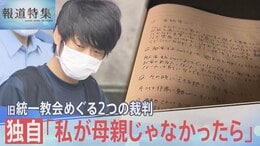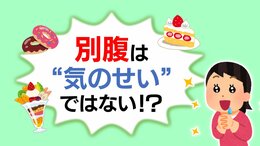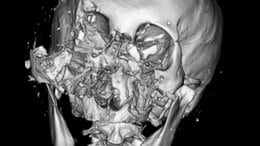実質賃金2.5%減少の衝撃
しかし、円安と価格転嫁は、日本国内の家計には大きな重荷です。
賃金が物価に追いつかないどころか、引き離される状況になっています。
6日発表された毎月勤労統計によれば、物価上昇分を差し引いた23年12月の実質賃金は、前年比1.9%の減少で、なんと21か月連続でマイナスです。減少幅は半年ぶりに2%を下回ったものの、プラスには程遠い数字です。
2023年通年でみると、実質賃金は前年比2.5%もの減少で、減少幅は22年の1.0%マイナスから大きく拡大しました。
物価上昇率が高かったことが実質賃金のマイナス幅拡大の大きな要因ですが、実は名目賃金の伸びが鈍化したことも効いています。
2023年の名目賃金である現金給与総額は、1.2%の増加で、2022年の2.0%増から増加幅が小さくなりました。
賃上げ機運が高まっているように見えるものの、実際に支払われた賃金の伸び率は低下していたのですから、「好循環に近づいている」をいう説明は、虚しく響きます。
実質賃金の伸び率に加えてもう一つ注目すべきなのは、実質賃金の水準そのものです。
2020年を100とした指数は、2023年は97.1でした。この数字は比較できる1990年以降では実は最低の数字なのです。
1990年の実質賃金指数は111.8、最も高かった96年は116.5でした。90年代初頭に比べて、実質の実入りはなんと貧しくなったことでしょうか。
実質賃金が少なくともプラスに反転しない限り、「好循環が始まった」とは、とても言えないでしょう。
企業と家計で全く異なる景況感
第一生命経済研究所の永濱利廣氏は、企業と家計の景況感の乖離が過去最高水準になっていると指摘します。
永濱氏によれば、企業=「日銀短観の業況判断指数」と、家計=同じ日銀の「生活意識に関するアンケート調査の景況感指数」を比較すると、歴史的には正の相関関係、つまり概ね同じような動きをしてきました。
企業の景況感が良くなっている時は、家計の景況感も良くなっていくというわけで、確かに自然な流れです。
しかし、2022年後半以降、企業の景況感がどんどん改善しているのに対し、家計の景況感指数は悪化し、真逆の動きをしているのだそうです。
永濱氏は、「景気判断が困難になっている」と言います。
可処分所得を増やす政策こそ最優先
家計の景況感を好転させるには、春闘などを通じて名目賃金を可能な限り引き上げると共に、物価上昇を緩やかにすることが必要です。
インフレをモデレートにするための円安是正も有効な手段です。
これに加えて岸田政権は、6月の定額減税実施を通じて、実質所得をプラスに導くシナリオを描いています。
そうだとすれば、家計の負担増を求める政策は、少なくとも今は、封印すべき時でしょう。
「子育て支援金」と称して医療保険料を引き上げ、岸田総理の言う「粗い試算」で、「1人月500円弱の負担増」を求める案など、もってのほかです。
経済政策に整合性が必要な、とても大事な時です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)