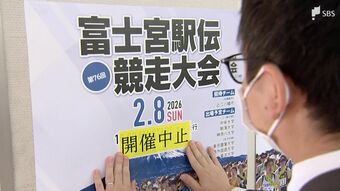能登半島地震では、静岡県内から行政職員が派遣されていて被災者のためにできることを模索しています。行政にできることが限られる中、地域住民同士の助け合いで乗り越えようとする姿もあり支援のあり方を問いかけています。
能登半島地震の発生から39日。被害の大きかった石川県能登町では、2月8日からようやくボランティアの受け入れが始まりました。石川県ではこれまでに241人が死亡、11人の安否がいまだわかっていません。
<東伊豆町住民福祉課 山田広美主査>
「天井が下がっているということなので、2次調査を希望されるならデメリットもあるんですけど、それでも2次調査申込みということであれば、いま罹災証明書をお出しするので」

先週、穴水町役場では、静岡県内の市や町から派遣された職員が罹災証明書の発行を行っていました。被害の程度によって、支援金が異なります。
<東伊豆町住民福祉課 山田広美主査>
「最初は『遠くからすみません』と言ってくださって、窓口に来てくれるんですけど、程度を知った時に表情が変わるのが目に見えてわかるのが切ないですね」
<静岡県職員>
「他の避難所を回りたいのですぐ僕も行きます」
穴水町では、静岡・奈良・栃木の職員が避難所の運営を行っています。

<栃木>
「県から派遣している職員だけで(運営を)できたほうがいいか、町の職員にいてもらった方がいいか」
<静岡>
「町の職員に昼間だけでも巡回してもらえればその時に相談できるかな」
<奈良>
「関わるフェーズが変わってきているんじゃないかということもある、今まだこの体制でいきましょうという議論も…」
山積する課題に葛藤しながらも被災者のためにできることを模索していました。