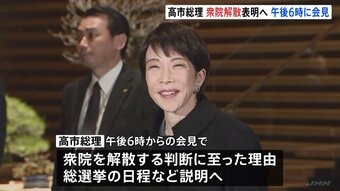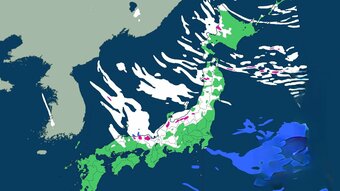日本銀行は、物価の先行きを見通す上で重視される「需給ギャップ」を公表し、去年7月から9月期がマイナス0.37%と14四半期連続でマイナスになったとの試算を発表しました。
「需給ギャップ」は日本経済の「需要」と「供給力」の差を示す指標で、内閣府と日銀がそれぞれ別の指標をもとに推計しています。
一般的に、「需給ギャップ」がプラスになると需要過剰でインフレに進みやすく、マイナスになると、供給過剰でデフレが進みやすいとされています。
日銀が9日に発表した推計では、去年7月から9月期の需給ギャップはマイナス0.37%となりました。
前回のマイナス0.15%からマイナス幅が0.22ポイント拡大し、14四半期連続でマイナスとなっています。
日銀は需給ギャップについて、去年10月の「展望レポート」で、「2023年度半ば頃にはプラスに転じ、プラス幅の緩やかな拡大が続く」と予想していますが、現状は想定を下回っています。
植田総裁は物価の先行きを見通すうえで、需給ギャップが重要な判断材料の一つになるとしていて、今月22日から開かれる金融政策決定会合の判断にどのような影響を与えるのか注目が集まります。
注目の記事
“空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行

立憲・公明が「新党結成」の衝撃 公明票の行方に自民閣僚経験者「気が気じゃない」【Nスタ解説】

「カツ丼」「貼るカイロ」の優しさが裏目に?共通テスト、親がやりがちな3つのNG行動「受験生は言われなくても頑張っています」

受験生狙う痴漢を防げ 各地でキャンペーン SNSに悪質な書き込みも 「痴漢撲滅」訴えるラッピングトレイン 防犯アプリ「デジポリス」 “缶バッジ”で抑止も

宿題ノートを目の前で破り捨てられ「何かがプツンと切れた」 日常的な暴力、暴言…父親の虐待から逃げた少年が外資系のホテリエになるまで 似た境遇の子に伝えたい「声を上げて」

「timelesz」を推すため沖縄から東京ドームへ――40代、初の推し活遠征で知った “熱狂” 参戦の味、そして “お財布事情”