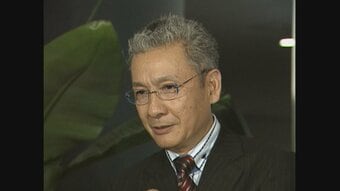グローバル経済の構造変化と経済安全保障
日米鉄鋼の盟主同志による大型再編を後押しした背景には、もちろん中国の存在があります。
中国は、今や世界最大の鉄鋼生産国、粗鋼生産業は年10億トンを超え、1億トン前後の日本やアメリカを大きく凌ぎます。
その中国が東南アジア市場をはじめとする世界に輸出攻勢をかけ、市況を悪化させる事態が、繰り返し起きています。
放しにすれば、一部製品の中国依存によってサプライチェーンの分断を招き、ひいては重要製品の調達にも影響が及びかねません。まさに経済安全保障に直結しています。
もはやアメリカの鉄鋼産業にとって、「敵」は日本なんぞではありません。
経済安全保障の利害が一致する日米の企業が連携を深めることで、高い成長と、一段の技術力を求めることは、時代の理にかなっています。
労働組合や議員から早くも反発
それでも、「鉄は国家なり」です。名門企業が外国資本に買われるとなれば、穏やかでない人たちも出てきます。
全米鉄鋼労働組合(USW)は合意が発表された直後に、買収反対の声明を出しました。「労働者が守られなくなる」という理屈です。
また、マルコ・ルビオ氏ら3人の共和党上院議員がイエレン財務長官らに「買収は阻止すべきだ」との書簡を送った他、民主党からも、USスチールのお膝元、ペンシルバニア州選出のフェッターマン上院議員が「阻止のためなら何でもする」と反対運動を予告しています。
「労働組合に最も近い」と自ら認めるバイデン大統領が、再選を目指す大統領選挙を前にどんな対応をするのか注目されるところですが、ホワイトハウスは21日、「たとえ親密な同盟であっても真剣な精査に値する」との声明を発表しました。
産業革命に端を発した工業化時代は、鉄こそが競争力の源泉であり、鉄がまさに「国力」そのものでした。
今や、工業化社会を卒業し、次の「情報化社会」や、その次の「5.0」の時代を迎えても、なお、人間の意識はなかなか追いつけない面があるのでしょう。
果たして、ついに鉄は国家を超えることができるか、時代が前に踏み出すところをしっかり見てみたいものです。見どころ満載の日米大型再編劇です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)