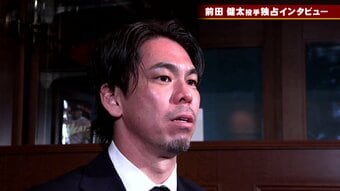きょう12月7日は、二十四節気の一つ「大雪」(たいせつ)です。「雪が大いに降り積もる頃」とされていますが、きょうの宮城県内は前線が通過するものの、降るものは雨が主体になる見込みです。この「二十四節気」ですが、きょうのように何だか実際の天気とは合わないなあと感じること、ありませんか?
二十四節気に違和感
例えば今年の2月4日、立春の日の仙台は、最低気温が氷点下3.1度まで下がり、青葉区の五色沼には一面氷が張って、春とは名ばかりの寒さとなっていました。一方、今年の8月23日、「暑さもおさまるころ」とされる処暑の日。しかしこの日は石巻で最低気温が27.4度と観測史上最も高くなり、最高気温は白石で35度ちょうどと猛暑日になった所もありました。暑さは全くおさまってはいませんでした。
このように、二十四節気は、我々の季節感よりも少し先走っているような印象があります。
仙台の平年の平均気温のグラフを見てみると、ちょうど立春(2月4日頃)のあたりが一年で最も寒くなっています。

2月はじめだと、まだ春らしさはなかなか感じにくいですよね。逆に立秋(8月7日頃)のあたりが一年で最も暑いということで、秋めいてきたなと感じられるのは、毎年9月に入ってからという人が多いのではないでしょうか。