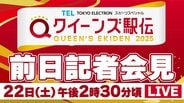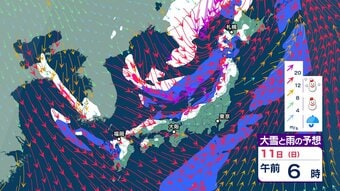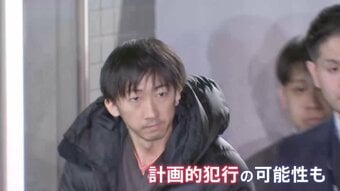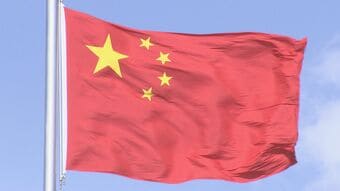高島の復活にフォーム改善と高い意識での取り組み
高島の故障はハムストリングス(大腿裏)や座骨が中心で、そこから複数の部位に痛みが派生した。昨年夏には痛みがなくなった。多血小板血漿療法(PRP療法。患者の血液を加工して組織の再生に関連する成分を抽出し、疾患のある部位に投与することで患者自身の体がもつ修復力をサポートし、改善に導く治療)も活用したが、一番は20年以降のフォーム改善など、高島自身の取り組みが功を奏した。
「動きを改善するトレーニングを、リハビリ期間中に行いました。筋力がなかったこともありますが、昔は力任せのがむしゃらな動きでしたね。腰が反り気味の姿勢で走っていて、ヒザが内側に入って外向きに蹴っていました。それがハムストリングや座骨に負担になったと思います。ヒザが内側に入らないよう筋力を付けて、筋力が付いている部位を走りに生かせる動きを目指しました。今の方が軸がしっかりしてブレないフォームで走れています」
高島は今年で35歳。上の学年は、興譲館高で1学年先輩だった新谷仁美(35、積水化学)くらいだろう。新谷は一度引退し、5年近く競技を離れている。良く言えば休養期間があった。高島の頑張りは賞賛に値する。
睡眠や栄養、ケアなどをしっかり行っている。高島自身は「練習量もしっかりやっていますし、前までは出された練習だけをやっていた感じですが、今はスタッフと話し合って、練習の意図を確認したり、こちらの体の状態を伝えて調整して練習している」と言う。
青野監督はケアに対する姿勢が、しっかり身に付いているという。
「これはチーム全体に指導していることですが、日本の実業団のケアに関する環境は、外国では考えられないくらいに恵まれています。それに甘えず、まずは自分の体は自分で理解する、自分でケアできることは自分でやる。その上で自分ではできないこと、どういう状態に自分の体をしたいかをトレーナーに伝えさせています。高島はその部分をしっかりとできるようになりました」
疲労の抜け方は年齢とともに遅くなり、強度の高い練習の入れ方には工夫が必要になってきた。それは事実だが、今も「練習はチームで一番やっている」と青野監督は認める。「若い頃も意識は高かったのですが、さらに高くなっている」。高島の復活の裏には、彼女の人並み外れた努力があった。
チームにとっては“同じ意味”の優勝になるが、高島にとっては…
優勝メンバーから1区と2区の区間賞選手が抜けたが、昨年の優勝と、今年優勝することの意味に「何の違いもない」と青野監督は言い切る。
青野監督は立命大、デンソー、そして昨年の資生堂と、コーチとして優勝に関わった。それらの経験から「駅伝で一番大事なのはチームワーク」という信念を持つ。
「去年の1、2区選手がいても、必ず勝てるとは限りませんし、その2人がいないから勝てない、とも限りません。特に違いは感じていませんね。チームワークが高まれば優勝できる。我々がやるべきことは昨年の自分たちを超えること、自分たちの力をしっかり出すことです。周囲から戦力が落ちたと思われてもかまいませんが、逆に燃えてきます」
5区の五島は前回、「昨年の自分を超える」ことだけを目標に走った。2位に36秒差のトップでタスキを受けたが、前半の5kmを区間記録のときより12秒速く入った。セーフティーと言えるリードで走り始めたが、青野監督も前半を抑えるように指示しなかった。多少失速しても、ブレーキを起こさない選手に成長していたからだが、「抑えさせたら良さが消えてしまう選手もいる」という判断だった。
後半でペースが落ちて逆に12秒届かなかったが、資生堂の“昨年の自分たちを超える”戦い方を考えれば、五島の前半の速い入りは意味があった。今年も五島が5区で力を発揮すれば、資生堂は強い。5区に起用できるかどうかは、他のメンバーの状態次第になる。
一山のMGCからの回復が不十分なら、5000mで15分27秒98を持つ井手が1区か。だが理想は一山が1区、高島が3区だろう。高島が3区で区間賞を取れないまでも、ライバルの積水化学に大差を付けられなければ、4区のジェプングティチと5区の五島で逆転ができる。
高島にとっては、今年優勝できれば昨年とは意味が違ってくる。
「昨年は強い子がたくさんいて、本当に頼れる後輩たち、頼もしいチームで優勝できました。今年は“自分もまだまだ走れるぞ”というところを見せたいと思っています。走りでチームに貢献する優勝にしたいですね」
デンソー時代に初優勝した13年からちょうど10年。自身5度目、資生堂の選手として2度目の優勝を果たしたとき、高島は何を感じるだろうか。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)