学校・病院などでの避難計画作成と訓練を義務付け
県は南海トラフ巨大地震の津波被害を防止・軽減させる対策として、今年3月、臼杵市・津久見市・佐伯市を「津波災害警戒区域」に指定しました。区域内にある学校や病院、社会福祉施設では避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられます。
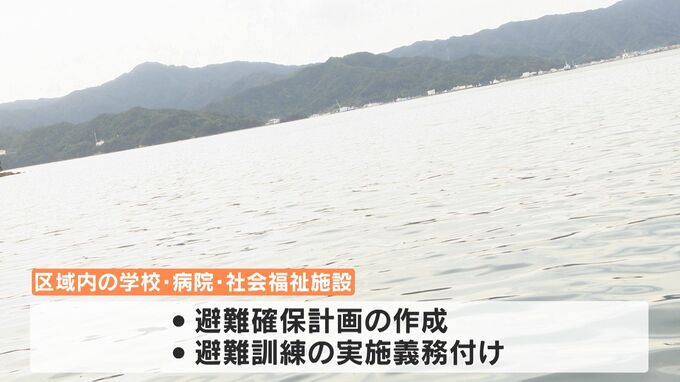
さらに、県は11月中にも別府市から中津市までの8市町村を追加。これで大分市を除く、海岸線のほぼ全域が指定される予定です。
「津波災害警戒区域」の指定は最大クラスの津波を想定しているものです。大分市もすでに南海トラフ地震に備えたハザードマップなどを作成していますが、別府湾地震が発生した場合、浸水範囲が広くなり、深さも大きくなる可能性が高いと見られています。このため、大分市は避難計画の見直しなど、指定に向けて課題の整理や調整を進めています。
(県建設政策課・緑川誠子さん)「発端は2011年3月の東日本大震災で、いざというときに逃げることができる地域として、県としても指定を進めている」
津波災害警戒区域に指定されて変わるのが「浸水想定」です。これまでハザードマップでは色の濃淡で津波の高さを示していましたが、新たな区域図では10メートル四方ごとに10センチ単位で最大時の高さが記載されます。
(緑川誠子さん)「建物に津波が当たったときの高さを考慮した水位が表示されるようになるので、具体的に避難する高さがわかりやすくなるのがメリット」
不動産業界は住宅地の評価額下落を懸念
また、不動産取り引きの際、業者は重要事項として物件の状態や権利の状況などと合わせて、津波災害警戒区域に入っていることを説明する義務が生じます。不動産業界では警戒区域の指定によって住宅地の一部で土地の評価額が下がる可能性を危惧しています。
(県宅地建物取引業協会・舛巴清人専務理事)「災害が発生するであろう場所に家を建てるのかどうかの部分で皆さん懸念するのではと思う。安心・安全な生活をしていく上では必要な区域決めだと思うので致し方ない」
津久見市の高齢者施設、施設長の小野さんは「災害は想定通りにはならない」とした上で、油断せず常に“万が一”を想定しておくことが重要と話します。
(「しおさい」・小野淳哉施設長)「入居者は特養の人は重度だし、その命をどう守るか、計画があっても現実に起きたときにいつ・どこで・どういう判断をするかは常時、考えていないとその時に慌てるので、自分自身でシミュレーションしておくことが大事と思う」














