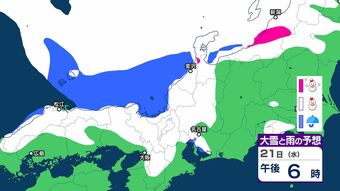■45万円はどこに使われたのか?元少年町長に伺う
では、実際の少年議会はどんな様子なのか?そして45万円はどんなものに使われるのか?2021年まで「少年町長」で、現在大学2年生の齋藤愛彩(あや)さんに伺いました。
――遊佐町ではどんな取り組みをしているのでしょうか?
元「少年町長」 齋藤愛彩さん:
私の時は、JRの駅や公共施設に、手作りのベンチを設置しました。
――なんでベンチだったのでしょうか?
元「少年町長」 齋藤愛彩さん:
JRは、電車が1時間に1本あるかないかで、下校の時間帯と丁度重なるので、駅が立っている学生であふれかえっている状態になるんです。一般の利用者にとって、すごく迷惑になっていたので、せめて座って頂ける場所だけでも欲しいよねということで、ベンチを設置しました。
――ベンチはどうやって作ったのでしょうか?
元「少年町長」 齋藤愛彩さん:
ベンチのデザインも、一から少年議会が考えて、町の工務店の方に「この形で作って下さい」ってお願いしました。あとは自分たちでペンキで絵を描いて、見ても楽しい、可愛いベンチを設置しました。
――実際作ってみて、どう感じましたか?
元「少年町長」 齋藤愛彩さん:
町に何かを作って影響を与えるのは大人だけなんじゃないかっていう感覚ももてたので、「自分にだって、町は変えられる」と、本気で思うようになりました。

予算を何に使うのか?議会ではまず、遊佐町の全中高生を対象にしたアンケートを取って、同世代のニーズを聞き取る事から始めるそうです。そうした中で、齋藤さんたちはベンチを作りましたが、その他にも、町の音楽イベントを実施したり、町の特産品のお米をモチーフにしたイメージキャラクターを作ったり、さまざまな施策が形になっているそうです。

■少年議会が大人の議会を動かすこともある!
町の予算を有効に形にしていく少年議会ですが、議論の中で、45万円の予算ではまかないきれない大きな計画が出てくることもあるそうです。
そうしたものは、大人の議会で協議されて、通学路に街路灯や雪よけの柵が設置されたこともあるそう。少年議会という若者の意見を、大人の議会がちゃんと取り入れる仕組みができているようです。
こうした取り組みもあって、遊佐町の若者の政治参加の意識は高まっています。2021年の衆院選では、遊佐町の18歳の投票率は、63.53%で、全国の18歳の50.36%を大幅に上回っていて、やはり、政治参加への意欲を示す若者が多いことがわかります。
■少年議会を卒業して続く政治参加への意欲
お話を伺った齋藤さんは、現在遊佐町を出て、山形市にある東北芸術工科大学のデザイン工学部コミュニティデザイン学科で、街づくりについて学んでいます。少年議会は卒業となりましたが、今も、政治参加への意欲が高いようです。

――現在は、どんなことをしているのでしょうか?
元「少年町長」 齋藤愛彩さん:
遊佐町を含む「庄内地域」の魅力を発信したいと思って、学生団体を立ち上げました。庄内地方に住む面白いと大人を取材しに行って、「自分たちの地元には、こんなに面白い人がいるよ」っていうのを紹介したり、新しい芋煮を提案しようとして「創作芋煮会」を行って、それをまた記事にして発表するとか。庄内をフィールドにやりたいことがあったら、とりあえずこのチームでやってみるようにしています。
――地元が大好きなんですね!
元「少年町長」 齋藤愛彩さん:
でも、中学校のときに同じクラスだった子たちに話すと、「あの頃のアヤちゃんは『絶対、都会に出て行ってやる!こんな田舎大っ嫌いだ!』って言っていたのが印象的」ということで、「まさかそんなアヤちゃんが遊佐町のために何かをしようとしていとは、びっくりだ!」って言われますね。少年議会に入っていなかったら、出会っていなかったら、こんな風には絶対になっていなかったと思います。
今は地元のために熱心に活動している齋藤さんですが、昔は大違い。周り一面、田んぼばかりで、近くにコンビニもない、何もない町に生まれ育った自分をすごく不幸に感じていたそうです。
それが、少年議会の活動を通して町の魅力と、自分の力で町を変えることができると知ったことで、いずれは遊佐町に戻って、遊佐町の教育に関わる仕事がしたいと思うようになったと話していました。
投票率の低下には様々な理由がありますが、こうした、「自分たちの未来は自分たちで決められる」という政治参加を学べる仕組みには、学べることもありそうです。
(TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」取材:田中ひとみ)