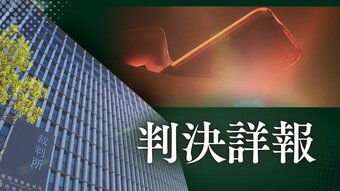◆交通インフラ整備で存在感を強める中国
先ほど、話に出た中国の「一帯一路」構想。この構想の最もわかりやすいケース(=モデルケース)がカンボジアだ。交通インフラを通じて、モノと人の往来を進めるのが、「一帯一路」構想だ。その一つとして、カンボジアではいま、中国の肝いりで鉄道建設プロジェクトが進む。
この路線はカンボジアの首都プノンペンから西北に進んで全長380キロ、タイとの国境の町ポイペトまでを結ぶ。線路敷設から車両まで、中国が支援する。これが完成すれば、やがて中国~ラオス~カンボジア~タイが鉄路で結ばれる。
鉄道だけではない。カンボジアで初めての高速道路が昨年11月に完成した。プノンペンと南部の港湾都市シアヌークビルを結ぶ約190キロの区間で、中国国有企業が約20億ドル(約2900億円)を投じて建設した。港から船で物資を出せるようになる。シアヌークビルには、中国が軍事利用する可能性が指摘されているカンボジア海軍基地もある。
◆中国との付き合い方に温度差
独裁体制が父から息子へ引き継がれて、国際社会から非難を浴びようが、カンボジアのように、中国に「頼る」「忠誠を誓う」国もある。ASEANなど国際会議で、一致して中国への非難ができないのも、カンボジアやラオスなど中国と関係の深い国の消極的な姿勢が存在するからだ。
一方で、ベトナムやフィリピンなどのように、南シナ海の領有権問題を抱え「警戒感を強める」国もある。
アメリカのバイデン大統領が最近、ベトナムの首都ハノイを訪問し、トップである共産党の書記長と会談した。アメリカとベトナムは、両国関係を新たに「包括的な戦略的パートナーシップ」に格上げすることで合意した。今後、安全保障や経済面での協力強化を図っていく。
両国は中国への警戒感を共有する。背景には、このインドシナ地域での中国の急ピッチの浸透が存在する。ASEAN10か国の中でも、中国との付き合い方に温度差があるようだ。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。