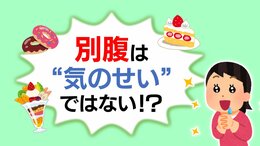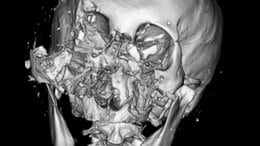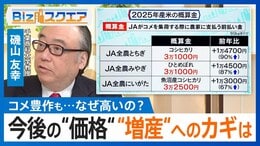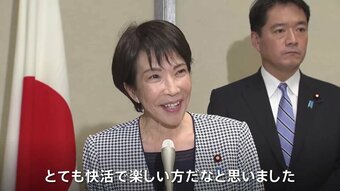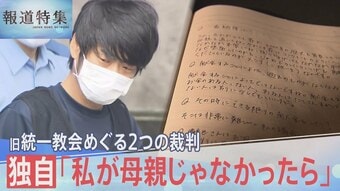いったん落ち着いていた原油価格が再び高騰し、世界経済のかく乱要因になりつつあります。原油価格の代表的な指標であるWTI原油先物価格は、5日、1バレル88ドル台まで値上がりし、2022年11月以来の高値となりました。
ウクライナ戦争が始まって1バレル100ドルを超えた時に比べればまだマシですが、2023年中盤に70ドル前後だったことを考えると、かなりの値上がりです。
産油国の減産が原油価格高騰の背景
今回の高騰は、産油国の減産が大きく効いています。サウジアラビアは同じ5日に、7月から続けている日量100万バレルの自主的な減産を12月まで延長すると発表し、需給がさらに引き締まりました。
アメリカなど先進国は、ウクライナ危機後、OPECなど産油国に増産を働きかけていますが、世界的な脱炭素・脱石油の動きに警戒感を強める産油国側は増産に応じないどころか、価格の高値安定を狙って、サウジのように自主減産までする状況です。
かつては、ほどほどのところでアメリカの求めに応じて来たサウジアラビアが、両国関係の悪化を受けて強硬派に転じてしまったことが、事態をより不透明にしています。
インフレ懸念再燃で米金利上昇
原油価格の高騰は世界経済に大きな影響を及ぼします。とりわけ、利上げ局面が最終段階を迎えているアメリカ経済には、原油価格の再上昇が、ようやく沈静化したインフレを再燃させる懸念があります。
そうした懸念が生じるだけで、金利高止まりの長期化を想起させ、すでに市場金利は上昇しています。
日米金利差の拡大によって、外国為替市場では円安が加速、7日には1ドル=147円台後半まで円安が進みました。昨年の円の最安値、151円が射程に入っています。
原油高と円安の同時進行が進む
石油を100%輸入に頼る日本経済にとって、原油価格の上昇はダイレクトにコスト高の影響を及ぼします。
また、原油高が一層の円安を招くことで、円建ての石油価格の上昇を一段と加速させてしまうからです。
原油高は、先に述べたように、日米金利差の拡大を通して円安を招くだけでなく、日本の貿易赤字拡大を通じても円安を招くというメカニズムも有しています。
日本のガソリン価格は、原油高と円安のダブルパンチでどんどん上がっているのです。