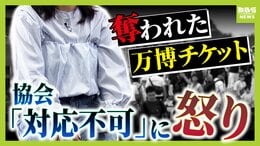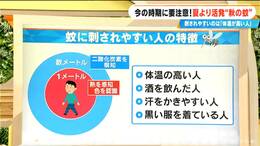どうする? 備蓄品の廃棄問題
地震への取り組み、続いては企業の工夫です。
東京・文京区にある凸版印刷の本社では、一部の奇数階と全ての偶数階に、食料や女性用品などが保管された備蓄倉庫が置かれています。元々は地下に置いていたのですが、過去の震災の経験から、エレベーターが使えなくても大丈夫なように変更しました。
取材すると72時間安心して会社にいられる備え、そして安心して家庭に帰る、帰るまでが防災というのも非常に勉強になりました。
ただ、取材した「凸版印刷」でも備蓄品を、かなり循環をさせてローテーションを組んでいますが「備蓄品の廃棄問題」が見えてきます。この課題に対して、ある取り組みをしている方々がいます。

【ストックベース】
災害備蓄品の廃棄削減をするということで、菊原美里さんと関芳実さんが始めた取り組みです。

大きな企業となると会社にある備蓄品が余ってしまいます。一方で子ども食堂など備蓄品を必要としているところがある。ここをマッチングして、ストックベースが中心となり、余ったものを渡す。このように、必要な分だけ準備ができるシステムがあるということです。改めて「自分の会社は大丈夫かな」と見直すきっかけになりました。
井上キャスター:
備蓄品が特別なものではなく、生活の中の食事の一つなんだというところに、考え方を持っていかないといけないのかなと思います。
山内キャスター:
会社も備蓄品を用意する時に、このあと子ども食堂で再利用しやすく、何かのメニューに使えるものを備蓄すればいいということですよね。だから品物の選び方も変わってきますよね。
井上キャスター:
全てが良いサイクルで回っていけばいいですよね。