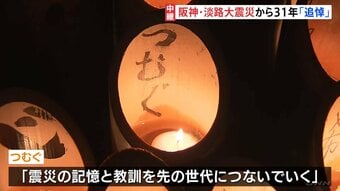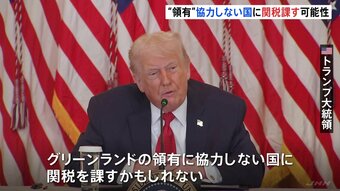補導してもまた“トー横”に…「無意味ではない」
小川彩佳キャスター:
これまで補導の現場も取材してきたということですが、今回の取材で新たな発見はありましたか?
窪小谷菜月 記者:
2年ほどトー横を取材している中で、補導された子どもがトー横に戻ってきてしまうということも目にしてきました。
しかし今回取材してみると、補導を繰り返すうちに、外泊していた子が終電までに帰るようになる、午後11時より前に帰るようになるなど、徐々に変わっていくこともあると知りました。

一見繰り返しているだけで、無意味に見えてしまうようなことでも、本人が自ら気づくまで向き合い続けてくれるひとの存在が、子どもにとって大きいのかなと感じました。
少年センターは、保護者と子どもが同じ職員とそれぞれ2人きりで話します。
センターの職員が親子の間に入り、親子をつなぐ役割を果たすことで、まずは保護者が救われます。
保護者の方と職員の方が、一緒に子どもに向き合うことで、子どもも変わっていくのだと感じました。
小川キャスター:
じっくりと自分と向き合う人がいるんだという、その安心感は計り知れないですよね。
データサイエンティスト 宮田裕章さん:
非常に重要なステップだと思います。今回の“トー横キッズ”の背景の一つとしては、「居場所がない」「家庭内で苦しい思いをしている」といった子どもたちがいる。SNSでよく集っていた子どもたちが、コロナ禍の社会現象として、“トー横”に集まってきた。これを目に見えなくしたとしても、苦しんでいる子どもたちは存在し続ける。根本的な課題に寄り添って向き合う。そういった取り組みは非常に大事なのだなと改めて感じました。
警視庁の相談受付「ヤング・テレホン・コーナー」
03-3580-4970