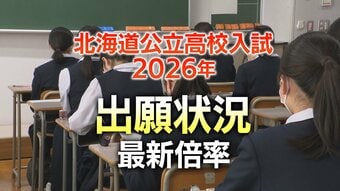「もっと早くに出会いたかった」

Yさん(19歳)は、たまたま見たネットの情報で星友館中学校のことを知りました。書店の倉庫で本の整理をしたり、出荷の調整をするバックヤードでのアルバイトがYさんの仕事です。「高卒の資格がほしい(本人談)」と感じていて、その思いが呼び覚まされ、アルバイトを続けながら去年入学しました。高校を1か月でやめてから3年目のことでした。
「勉強のレベルをそれぞれに合わせて対応してくれるのが、すごくいいんです」。
「いい学校に出会ったと思います。もっと早くに出会いたかったです」。
星友館中学校では上級レベルの「チャレンジコース」に在籍して、勉強の理解が進んでいるそうです。次の目標は高卒認定試験を受けることで、「それも現実的になって来ました(本人談)」と話します。

「ここ(星友館中学校)には『自分だけではない』と感じる安心感があるんです」。
「クラスには年上の人もたくさんいて、話しやすいんです。趣味のバイクの話で盛り上がったりするんです」。
Yさんは4月にバイクの免許を取り、休みの日にはツーリングに出かけたりしています。将来は警察官になって、白バイ隊員として働きたいと思っています。
警察官を志望するきっかけは、不登校を経験した時のある日のことでした。家に引きこもっていて母親とけんかになり、自ら警察に通報して仲裁してもらったことがありました。その時の警察官の対応が心に残り、「同じような少年の気持ちは、自分がよく理解できるのかな(本人談)」と感じました。それは、自分にもできることがあるように思えた経験でした。
その後、Yさんは母親と和解し、時々実家に帰りながら、アルバイトと学び直しを続けています。
・・・・・・・・

不登校を自らも経験し、現在、不登校に関する情報を発信している「不登校新聞」の編集長、茂手木涼岳(もてぎ・りょうが)さん(42歳)に聞きました。
「小中学生の不登校の数が過去最多となったことについては、取材をしている感覚では、学校がストレスフルな環境になっていることがあります。教員は忙しく、担任を校長や教頭が兼務している所もあって、目が行き届いていない。また、“脱ゆとり教育”の影響でいじめが低年齢化していることもあるようです。そもそも不登校自体は問題でありません。不登校で子どもや親が苦しむことが問題なんです。不登校の子には、落ち着くことができて、『ここに居てもいいんだ』と感じてもらう場が必要です。親も自信がないんです。子育てには正解がありませんから。子どもが不登校になると、親はママ友などのコミュニティから出されて孤立してしまいますので、そうした親に私たちは『親コミュ』というオンラインでつながって、まずは『お子さんをじっくり抱きしめて下さい』と伝え、様々な体験談を共有しています。夜間中学には、私もかつてボランティアとして生徒さんや教員のサポートをしたことがありますが、これから入学する人たちに向けて、例えば不登校経験者や外国出身者がそれぞれどれくらいの割合在籍しているかなど、細かな情報をどんどん発信してほしいと期待しています」。
【連載記事のラインナップ】
・プロローグ 開校2年目の夏~札幌市立星友館(せいゆうかん)中学校
・エピソード(1)モロッコと清龍~異国で生まれ育ったある日本人の場合 その1「思い出したくもない過去」
・エピソード(2)モロッコと清龍~異国で生まれ育ったある日本人の場合 その2「奇跡の来日」
・エピソード(3)農作業と入院~少女時代を取り戻す82歳と72歳の青春
・エピソード(4)同級生の前にさらされて…不登校経験者・Y(19歳)
・エピソード(5)「虐待で育ったから…」父子で通う同級生親子
・エピソード(6)3時起床23時就寝~もっと勉強したい56歳
・エピソード(7)モロッコと清龍~異国で生まれ育ったある日本人の場合 その3「再びホームレスと…」
*注1)不登校新聞:NPO法人全国不登校新聞社(東京)が発行する不登校の情報の専門紙です。1998年に創刊し、「学校で苦しむ子どもが安心して生きていける社会をつくる」ことを掲げ、不登校・ひきこもりの当事者・経験者・親の声や教育行政の動きなどを紙面とオンラインで発信し、講演や関連の出版も手掛けています。
*注2)中学校既卒者の再入学を認める措置について:文部科学省は「中学校の課程の大部分を欠席していた又はそれに準ずる状況であった等の事情により、実質的に義務教育を十分に受けられておらず、(中略)再度中学校に入学を認めることが適当と認められる」入学希望者には「積極的に入学を認めることが望ましい」という通知を、2015年に全国の市町村教育委員会に出しました。それまで既卒者は中学校への再入学を認められていませんでしたが、この通知によって希望者は公立の夜間中学校へ入学できるようになりました。
*注3)札幌市立星友館中学校は、入学を随時受け付けています。9月から12月までの間に受け付けの場合は来年4月入学となり、来年1月から8月までの間に受け付けの場合は来年5月から10月までの間の入学となります。詳細は同校へお問い合わせください。
◇文: HBC・油谷弘洋