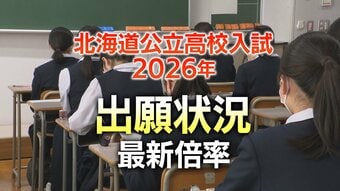なぜ学ぶのか?なぜ学ぶことができなかったのか?

札幌の繁華街、すすきのにネオンが灯る頃、その学舎(まなびや)に人々が通学して来ます。札幌市立星友館中学校は、すすきのに隣接する一角に、去年4月開校した北海道で唯一の公立夜間中学校です。高齢者、不登校経験者、外国出身者…通うべき時期に中学校へ行くことができなかった人たちが在籍しています。10代から80代までの多様な老若男女が、中には過酷な体験をした人が、夜の帳(とばり)の降りた校舎に机を並べています。なぜ学ぶのでしょうか?なぜ学ぶことができなかったのでしょうか?何を求めて集うのでしょうか?星空の下、学び直しをする人々のそれぞれの事情と姿をお伝えします。
エピソード(4)は、同級生の前にさらされて…不登校経験者・Y(19歳)です。
同級生の前にさらされて…

星友館中学校が去年開校した時の1期生の1人が、Yさんです。19歳の男性で、不登校を経験しました。
穏やかな表情ながら、私を見据えて、ここまでの道のりをゆっくりと語りました。
勉強は小学生の頃から苦手で、授業のペースについて行けないことがありました。中学校に進んでからはバトミントン部に入り、生活委員会の活動も始めました。帰宅後は疲れて予習や復習に手をつけられない日が多く、授業がわからなくなって欠席が増え、学校が遠い存在になって行きました。当時、最も辛かったのは、授業で黒板の前に出て問題を解かされることでした。考えても考えても答えは出てこず、そんな姿で同級生の前にさらされていることが「きつかった。配慮してほしかった(本人談)」そうです。
それでも中学校は卒業した形となり、定時制高校に進学しましたが、1か月で退学しました。それは親と対立する原因となり、ひきこもり、時には暴力的になることもありました。そして家を出て、アパートで一人暮らしを始めました。家賃は母親が支払ってくれました。以来、アルバイトだけをしながら過ごす日が続きます。
24万人超…小中学生の不登校が過去最多

文部科学省の最新の調査によりますと、小中学生の不登校は24万4940人(2021年度)です。この数字は前年度(19万6127人)から24.9%大幅に増えて過去最多となり、初めて20万人を超える状況となりました。
不登校が大幅に増えた背景について文科省は、「児童生徒の休養の必要性を明示した教育機会確保法の趣旨の浸透」「新型コロナウイルスによる生活環境の変化」「コロナ禍のもと学校生活においてさまざまな制限があるなかで、登校する意欲がわきにくい状況」などが考えられるとしています。
また、その要因について文科省は、児童生徒本人の「無気力・不安」が49.7%で最も多いとし、次いで児童生徒本人の「生活リズムの乱れ・あそび・非行」が11.7%などで、最も少ない要因は「いじめ」の0.2%としています。
この調査については、教員が回答しているため、実態に即していないという批判もあります。