「長年日本のために働いてきたが…」
難民認定後、半年間は生活費や住居費などの支援を受けることができる。その間に住居や仕事を探し、自立を目指す。
最大の壁は日本語だ。アフガニスタン本国の業務では日本語はほとんど使う機会がなく、職員間では英語でコミュニケーションしていた。
政府の支援事業を委託されている難民事業本部(RHQ)から学習支援を受けたが、半年足らずの期間では、自立した生活を送れるレベルには達しなかった。
「例えば病院やクリニックに行くとき、日本語ができないと診察してもらえないことがあります。子どもたちの学校とのコミュニケーションの問題もあります」
日本語の習得は多くの人にとって大きな課題となっているとみられ、難民事業本部も「国からの委託事業とは別に、独自に日本語フォローアップ授業を行うこととし、すでに開始している」と言う。
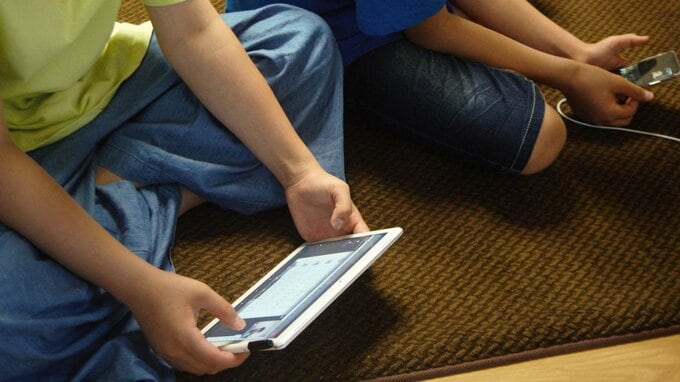
子どもの教育についても不安を抱える。アフマドさんの子どもたちのうち、15歳以下は小中学校に通っているが、日本の高校生以上の子どもたちは最近、ようやく語学学校に通い始めたばかりだ。
アフマドさんは現在、タクシー会社で短期の契約社員として働いているが、7月の収入は手取りで11万円弱。3月以降は生活費の支援もなくなり、家族を養うのにはとても足りない。
そんな中でも、母国で危険を避けるため住居を転々としている両親らにも給料の一部を送っている。
厳しい現実に直面するアフマドさんが複雑な思いを感じているのが、ウクライナ避難民への日本政府や社会の支援だ。就労や就学支援、社会との関わり、あらゆる点で自分たちとは大きな差があると感じている。
「我々は長い間、非常に危険な状況下で日本政府のために働いてきた。ウクライナの人々と、私たちとの間になぜこれほど違いがあるのか理解できません。髪や、肌の色のせいですか?」
外務省はアフガニスタンの難民について「個別に相談に乗るなど、可能な支援は続けたい」としているが、アフマドさんの孤立感は日に日に高まっている。
「誰も『日本での暮らしはどうですか』、そんな言葉をかけてくれはしません」
「私たちはアフガニスタンに帰ることはできない。日本で暮らしていくことも難しい。それならばせめて、第三国に我々を移してほしいです」
すでにアフマドさんが知る複数の家族が、危険を承知で帰国を決断したという。自らも帰国が頭をよぎるが、戻れば必ず迫害を受ける、と訴えた。














