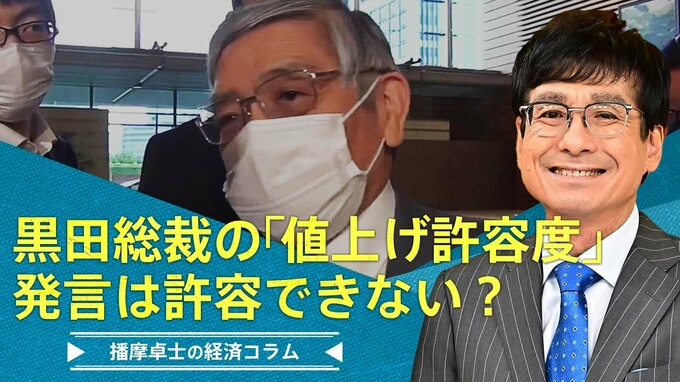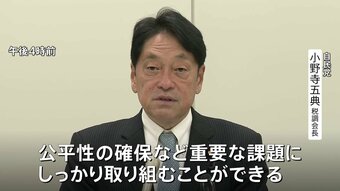中央銀行である日銀総裁の発言がこれほどまでに軽いものなのかと呆れました。日銀の黒田総裁が、6月6日の講演で「家計の値上げ許容度も高まってきている」と述べたことについて、批判が高まり、翌7日に「適切ではなかった」と釈明したのに続き、同日夕刻には「誤解を招き申し訳なかった」と謝罪、さらに、その翌8日には、全面撤回に追い込まれました。黒田総裁の「値上げ許容度発言」は、「失言」として歴史に記録されようとしています。
しかし、当日の映像を見れば、黒田総裁が思いつきや勢いで口に出した発言でないことは明白です。共同通信主催の講演会という場、必ず記事にされることを前提にした講演ですから、黒田総裁は用心深くずっと原稿を読んでいます。英才エコノミスト集団たる日銀事務局が練りに練った原稿です。物価の番人たる中央銀行の本分である「物価見通し」について、総裁が述べるのですから周到な準備がされて当然です。そこにこそ、問題の深刻さがあります。
「家計」「許容度」「強制貯蓄」といった用語の語感、一般的な受け止められ方に対する感度が低いばかりか、特定の調査の一部分だけをもとに結論を導く安易さ、物価高に直面する国民生活への配慮の欠如などは、すでに批判を受けている通りです。2%の物価目標を掲げながら、目標達成ができず、「言いっ放し」が足掛け10年にも及んだからなのか、「あとは賃上げを待ちます」的な姿勢、その「他人事」感には驚かされます。そこには「もうすぐうまく行きます」と、手っ取り早く、自らの政策を正当化したいとの意図すら透けて見えます。
しかしその一方で、黒田総裁の発言がすべて誤りかといえば、必ずしも、そうではないでしょう。黒田総裁の言う「家計」とは「我が家の家計」ではなく、経済学で使うところの経済主体の「総体としての家計」のことですし、この場合の「許容」も「私が受け入れている」という「主観」ではなく、値上げ後の取引価格で引き続き取引が成立しているかどうかという「事象」であり、全体としての「耐性」を意味しているからです。
値上げの動きが多品目に広がり、その頻度も増えていて、個人的に許せるかどうかは別としても、実際に値上げ後の価格で取引が行われるようなことは、少なくとも、これまでのデフレ時代には見られなかったことです。「まだ仮説かもしれないが、ひょっとしたら良い物価上昇につながるかもしれない、そのために是非とも政府も企業も今こそ賃上げを!」黒田総裁がこう言っていれば、受け止め方は違ったのではないでしょうか。
今、必要なことは、エネルギーや原材料高騰による物価上昇があっても、消費が落ちないように目配りしながら、いかにして本格的な賃上げにつなげるか、という議論のはずです。コロナ明けの「リベンジ消費」が息切れしないうちに、財政による家計支援など広範な政策が必要な、大事な時期であるように思えます。黒田発言を「失言」扱いすることで、過去30年、日本に訪れることがなかった、デフレ脱却のチャンス(不発に終わる可能性もありますが)を活かすための議論が封じられるのであれば、非常に残念なことです。成長と賃上げの好循環を作るための前向きの議論なら、許容できるのではないでしょうか。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
注目の記事
愛媛県民は「を」を「WO」と発音? 47都道府県調査で見えた驚きの「常識」

「米はあるのに、なぜ高い?」業者の倉庫に眠る新米 品薄への恐怖が招いた“集荷競争”が「高止まり続く要因に」

大阪王将 ドーナツ業界に進出「ぎょーナツ」餃子味、麻婆豆腐味って? 異業種が参入するワケ【Nスタ解説】

1枚500円なのに交換は440円分…農水大臣が「おこめ券」にこだわる理由、百貨店商品券との違い【Nスタ解説】

「武蔵が沈んだ…」部下を思い、涙した初代砲術長・永橋爲茂 戦後なぜ、家族を残し一人島で暮らしたのか #きおくをつなごう #戦争の記憶

「BYD」「テスラ」米中2大EVメーカーが北海道進出《なぜ?》「北海道はブルーオーシャン」寒冷地でEVは普及するのか「ノルウェーでは93%のEV浸透」